がん患者様のためのお役立ちブログ


腹膜播種の余命とは? 症状や治療法、腹膜がんやがん性腹膜炎との違いについても解説
腹膜播種(ふくまくはしゅ)とは、がん細胞が腹膜に散らばり広がる状態を指します。
原発巣からの遠隔転移とみなされるため、一般的にステージ4と診断されます。
そこで気になってくるのが、「余命はどれくらいなのか?」「治療は可能なのか?」という点ではないでしょうか?
今回の記事では、腹膜播種の特徴や治療法、そして気になる余命について解説していきます。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
腹膜播種と余命
腹膜播種が確認された場合、その後の経過や日常生活を維持できる期間(いわゆる「余命」)について不安を感じる方も多いでしょう。
腹膜播種が確認されたからといって、余命宣告される訳ではありません。腹膜播種の広がり具合や原発がんの種類、全身状態、治療への反応など人によって状況はさまざまなためです。
例えば、腹膜へのがんの広がりが限局しており、他の臓器に転移していない場合は、治療がうまくいくケースが多いです。
一方で、播種の範囲が広く腹水の貯留や合併症がある場合は、治療選択肢が限られ余命宣告をされる場合もあります。ただし、状況には個人差があるため一概に期間を断定することはできません。
以下は、腹膜播種の経過を判断する材料です。
| 播種の範囲・進行度 | 限局していれば比較的良好、広範囲だと予後不良の可能性 |
| 抗がん剤の効果 | 効果が高いほど長期の日常生活維持が期待される |
| 合併症や全身状態 | 栄養状態や感染症の有無も影響する |
治療の進歩により、かつてよりも状況が改善している例もあり、個別の状況に応じた治療を受けることができます。
腹膜播種とは?

腹膜播種とは、がんが進行する過程で、がん細胞が腹膜と呼ばれるお腹の内側を覆う膜に広がっていく状態を指します。
これは、がんの転移の一種であり、特に胃がん、大腸がん、卵巣がんなどでよく見られます。
本来、がんは発生した臓器の中で増殖しますが、進行すると周囲の組織や他の臓器に広がることがあります。
腹膜播種は、その中でもがん細胞が血管やリンパ管を通らず、腹腔内に直接ばらまかれるように広がる点が特徴です。
これにより、腹膜全体や腸の表面、さらには腹水と呼ばれる液体内にもがん細胞が見られるようになります。
腹膜播種の症状|腹水との関係
腹膜播種の主な症状は、お腹の張り(腹部膨満感)や体重減少、吐き気・嘔吐、食欲不振、便秘、腹痛などです。
これらの症状は、がん細胞が腹膜に広がることで腹水が溜まることや、腸の動きが悪くなる(腸閉塞)ことによって起こります。
進行すると、体への栄養吸収が妨げられ、全身の倦怠感や呼吸困難を引き起こし、短期間で重篤な状態になることもあります。
主な症状
- お腹の張り(腹部膨満感)や体重増加
- 吐き気、嘔吐、食欲不振
- 便秘や腸閉塞
- 腹痛
- 体重減少
- 全身の倦怠感
- 呼吸困難
関連記事:がんで腹水がたまってしまったときの余命は? 腹水の治療法や同時に検討したいがん治療
腹膜播種の原発巣
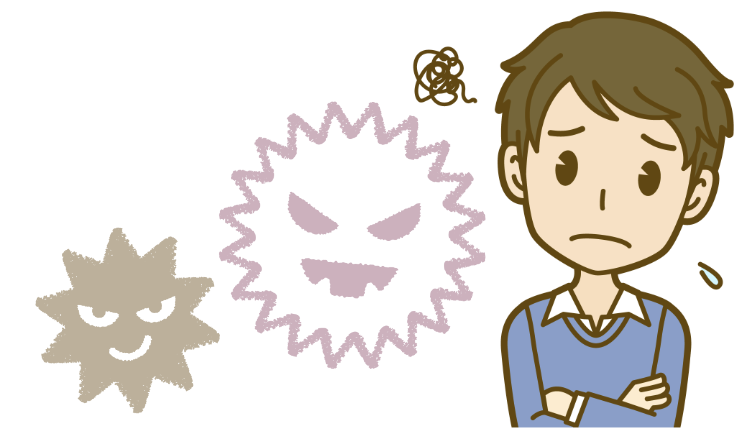
腹膜播種は、主に消化器系や婦人科系のがんから発生することが多く、原発がんの種類によって特徴や進行の仕方が異なります。
ここでは、腹膜播種を引き起こしやすい代表的ながんについて解説します。
胃がん
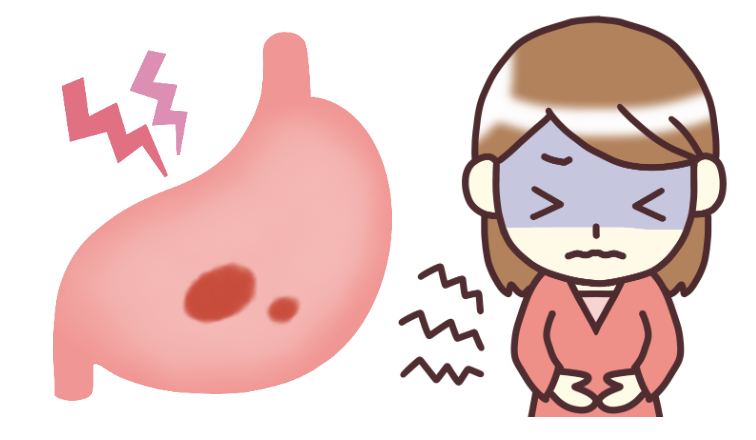
特に進行した胃がんでは、がん細胞が胃の壁を突き破って腹腔内に漏れ出し、腹膜に散らばることで腹膜播種が発生します。
これはスキルス胃がんと呼ばれるタイプに多く見られ、がん細胞が広範囲に浸潤しやすい特徴があります。
腹膜播種が起こると、腹膜の表面にがん細胞が付着・増殖し、やがてがん性腹膜炎や腹水の貯留を引き起こすこともあります。
関連記事:「スキルス胃がんは完治する?」
大腸がん
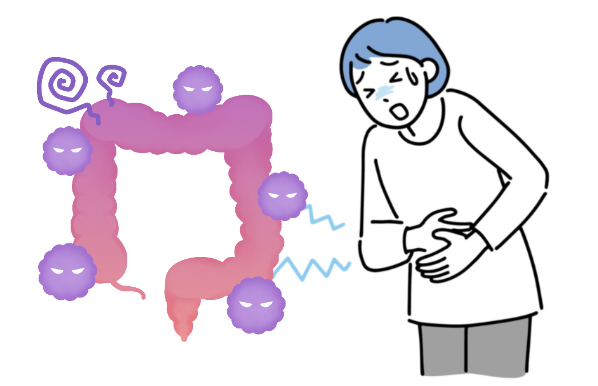
特に進行した大腸がんや再発時に、がん細胞が大腸の壁を突き抜けて腹腔内に散らばることで、腹膜に付着・増殖し、腹膜播種が生じます。
特に、直腸やS状結腸といった腹膜に近い部位のがんでは、腹膜播種のリスクが高まる傾向があります。
また、大腸がんでは肝臓や肺への転移がよく知られていますが、腹膜播種は比較的進行した段階で見つかることが多く、治療の難易度が高いのが特徴です。
関連記事:「大腸がんのステージ4とは?」
卵巣がん
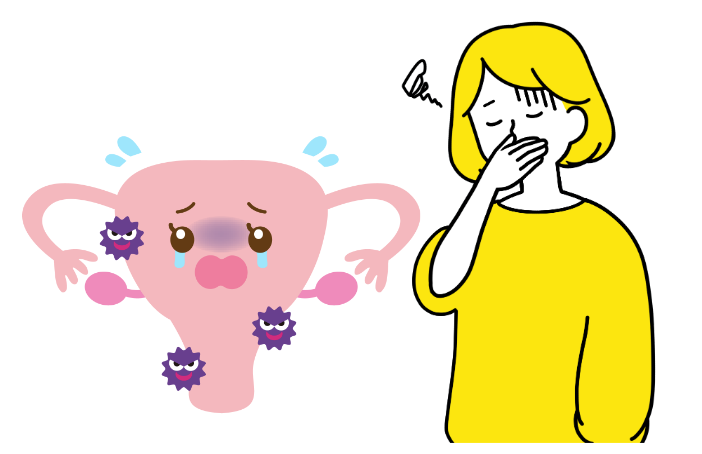
卵巣は腹腔内に位置しており、がん細胞が腹膜へ直接広がりやすいため、初期の段階から腹膜播種が見られることも珍しくありません。
卵巣がんの腹膜播種は、がん細胞が腹水中を漂いながら腹膜に付着し、複数の部位に腫瘍を形成することで進行します。
特に「漿液性腺がん」は腹膜播種の頻度が高く、がん性腹膜炎や腹水の貯留を伴うケースも多く見られます。
関連記事:「卵巣がんで余命宣告を受けたら?」
腹膜播種の治療法

腹膜播種の治療は、がんの種類や進行度、患者さまの全身状態によって大きく異なります。
ここでは、主に行われている代表的な治療法について解説します。
手術
腹膜播種に対する手術は、がんの広がりが限られている場合に限り、治療の選択肢となることがあります。
特に、原発巣と腹膜上の腫瘍を一括で切除できると判断された場合には、「完全切除(R0切除)」を目指す手術が検討されます。
また、一部の医療機関では、手術と温熱化学療法(HIPEC)を組み合わせる治療も行われており、一定の効果が報告されています。
関連記事:「温熱療法とは?」
化学療法
化学療法(抗がん剤治療)は、腹膜播種に対して広く用いられている基本的な治療法です。
全身に作用する薬剤を使うことで、腹膜に散らばったがん細胞を抑えることが期待されます。
特に、腹膜播種が広範囲にわたる場合や、手術による切除が難しいケースでは、化学療法が主な治療手段となります。
使用される薬剤は、原発がんの種類に応じて異なり、胃がんならS-1やシスプラチン、大腸がんならFOLFOXやFOLFIRIなどが代表的です。
また、一部の施設では、腹腔内に抗がん剤を直接投与する「腹腔内化学療法」が行われることもあります。
緩和ケア
緩和ケアは、がんの進行に伴うつらい症状を和らげ、生活の質(QOL)を保つことを目的とした医療です。
腹膜播種では、腹痛や腹部の張り、食欲不振、倦怠感などが生じやすく、これらに対して適切な緩和が求められます。
治療が困難な場合でも、緩和ケアによって患者さま本人の希望に寄り添いながら、身体的・精神的な負担を軽減することが可能です。
主な緩和ケアの内容は以下のとおりです。
| 緩和ケアの例 | 内容 |
| 痛みや不快感の緩和 | 鎮痛薬の使用、腹水への対処など |
| 精神的サポート | 不安や抑うつへの対応、家族とのコミュニケーション支援 |
| 栄養・生活支援 | 食事の工夫や在宅ケアのサポートなど |
緩和ケアは終末期に限らず、がんと診断された段階から推奨されています。
免疫療法
免疫療法は、本来人間が持っている「免疫」の働きを活性化させる治療法です。
従来の抗がん剤のように直接がん細胞を攻撃するのではなく、免疫細胞ががんと闘う力を高めることで、身体全体でがんを抑え込むというアプローチが特徴です。
特に副作用が比較的少ない点や、がんの種類によっては高い効果が期待できることから、注目されています。
腹膜播種においても、免疫療法は新たな治療選択肢として期待されています。
なかでも、複数の免疫細胞を利用した「6種複合免疫療法」は、がんとの長期的な共存や再発予防を目指す治療法です。
以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
腹膜播種と腹膜がん・がん性腹膜炎の違い
前述の通り、腹膜播種はがん細胞が腹腔内に散らばり、腹膜に転移して増殖する状態を指します。
これはあくまで他の臓器に発生したがんが広がった結果であり、原発巣(最初にがんができた場所)は別にあります。
一方で、「腹膜がん(悪性腹膜中皮腫)」は腹膜そのものに最初に発生するがんです。
これは非常に稀で、特に女性に多くみられる「原発性腹膜がん」が代表的です。
卵巣がんと似た性質を持っており、診断や治療も共通する部分があります。
また、「がん性腹膜炎」とは、腹膜播種が進行し、がん細胞が腹膜全体に広がって炎症を起こし、腹水がたまるなどの症状を引き起こしている状態を指します。
これは腹膜播種の末期にみられることが多く、強い腹部膨満感や痛みなどを伴います。
それぞれの違いは以下のとおりです。
| 名称 | 原発部位 | 特徴 |
| 腹膜播種 | 他の臓器 | 転移性。腹膜にがんが散らばる状態 |
| 腹膜がん | 腹膜自体 | 原発性。発生頻度は低い |
| がん性腹膜炎 | 他の臓器 | 炎症や腹水を伴う腹膜播種の末期状態 |
関連記事:「がん性腹膜炎とは?」
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








