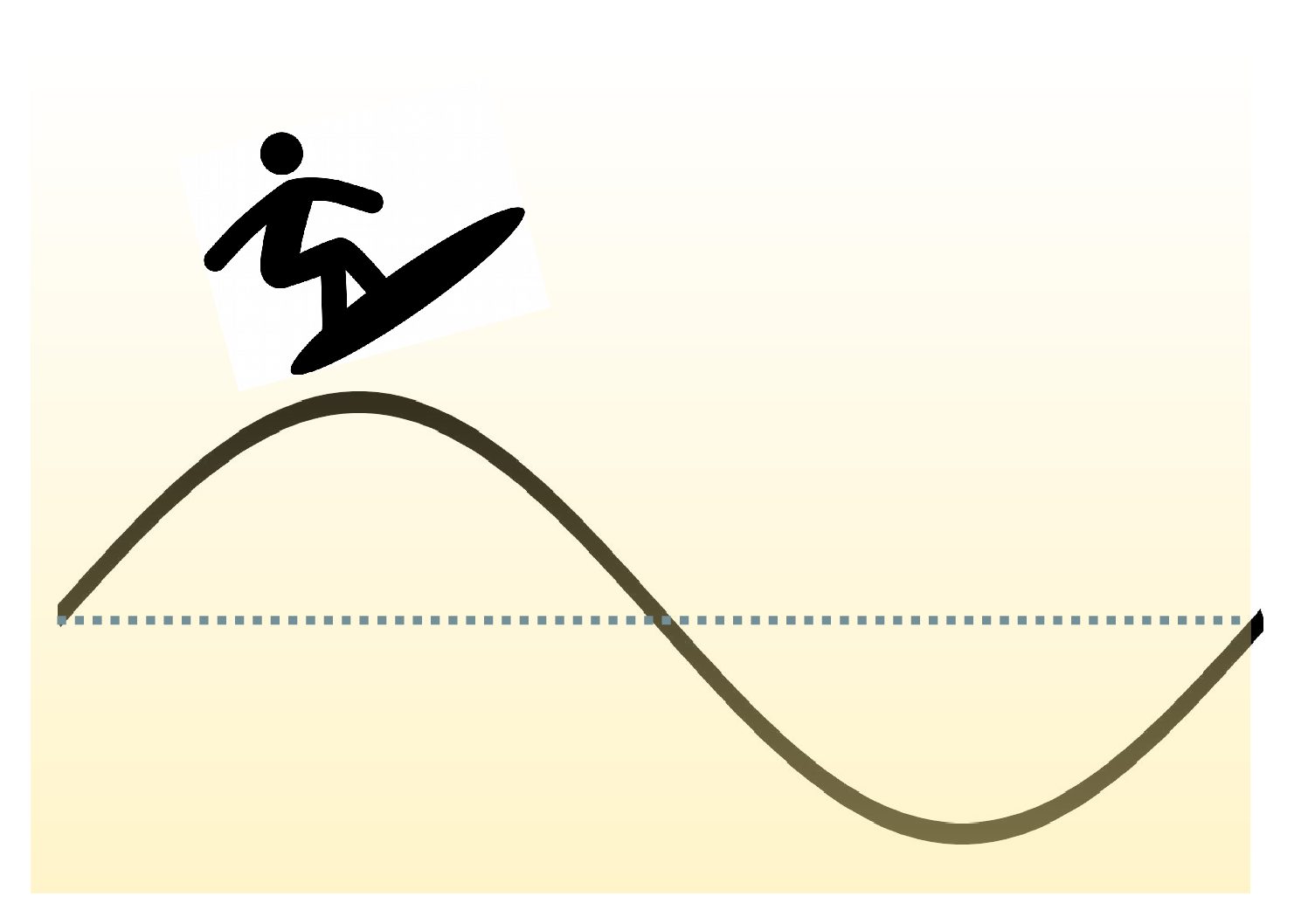がん免疫療法コラム


情報屋、樹状細胞!《自然免疫と獲得免疫の架け橋》
以前Vol.1で、がん免疫療法ではリンパ球が大切であると説明しましたが、それと並んで重要な免疫細胞があります。それは樹状細胞です。2011年にノーベル賞を受賞したラルフ・スタインマンによりその存在や働きが明らかにされました。がんワクチンなどの免疫療法の中核を成すとても大事な免疫細胞なので、今回はこの樹状細胞の働きについて見て行きたいと思います。そして、免疫反応における重要な働きが明らかになった後でも、長らくその真価が認められない不遇の時代がありました。一体なぜでしょう。その理由についても併せて見て行くことにしましょう。
■樹状細胞の働き
◇自然免疫と獲得免疫のつなぎ役
免疫反応は大きく2つに分かれます。一つが自然免疫、もう一つが獲得免疫です。自然免疫は、主に好中球やマクロファージ、樹状細胞といった食細胞が担当しています。侵入してきた異物や異常が生じた細胞を見つけ、それを直接、排除する仕組みです。
もう一つの獲得免疫とは、先ほどの自然免疫に引き続いて起こる免疫反応です。異物の特徴を記憶することで、再度侵入、または発現した異物を効果的に排除する仕組みです。樹状細胞は、異物との戦いの現場に出向き、異物などを飲み込むことにより、情報を取得します(自然免疫)。そして、他の免疫細胞にその情報を伝え、活性化します(獲得免疫)。
◇情報の収集と伝達役
以上のように樹状細胞は情報の収集と伝達を通じて、2つの免疫反応をつなぐ非常に大切な働きをします。ここでの情報の収集とは、異物の一部を体内に取り込み、そこから異物の特徴を示す断片を取り出す働きを意味します。例えるなら異物のIDを作るようなものでしょうか。
そして情報の伝達とは「抗原提示」を指しています。「抗原提示」とは樹状細胞が細菌やウイルスなどの異物を捕まえると、血管やリンパ節からリンパ節へと移動し、そこに待機しているT細胞に異物の断片、つまり先のIDを提示することを言います。T細胞にIDを見せて、それを覚えてもらいます。その後、キラーT細胞やB細胞が活性化し、がんなどの異物への攻撃が始まります。
■ブレイクスルー
1973年に樹状細胞に関する論文がスタインマンにより初めて発表され、その存在と形態的な特徴が示されました。続いて、その働きが証明されるなど研究が進められましたが、すぐにこれらの研究に対する評価が得られた訳ではありませんでした。その理由として、この細胞が見つけにくく、培養が難しかった点が挙げられます。
最初の論文発表から二十年近くかけてようやく樹状細胞の培養方法が確立され、論文として発表されたのは1992年のことでした。サイトカインである顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)が樹状細胞の増殖因子であることを実証した画期的な内容の論文でした。実は、この論文の筆頭著者は日本人で、現京都大学副学長の稲葉カヨ氏がその人です。免疫学は日本のお家芸と言われていますが、それを代表する一人と言えます。
最終的には1998年に培養に関する材料や方法についてまとめた論文が発表され、これを機に樹状細胞の知名度は一気に上りました。そして、それと共に様々な疾患に対する治療へと臨床応用が進み、冒頭のノーベル賞の受賞へと至りました。
このように樹状細胞は自然免疫と獲得免疫をつなぐ架け橋のような存在であり、自然免疫の中では異物に関する情報収集を担い、獲得免疫の中ではその伝達を担っていること、そしてこれらが認知されるまでにちょっと時間がかかった理由をお分かりいただけたと思います。
次回は樹状細胞を用いることにより生み出された「がんワクチン療法」について見て行きたいと思います。
参考文献
- ニール・キャナブン,がん免疫療法の誕生, 2018
- 岸本忠光, 中嶋彰, 免疫が挑むがんと難病, 2016