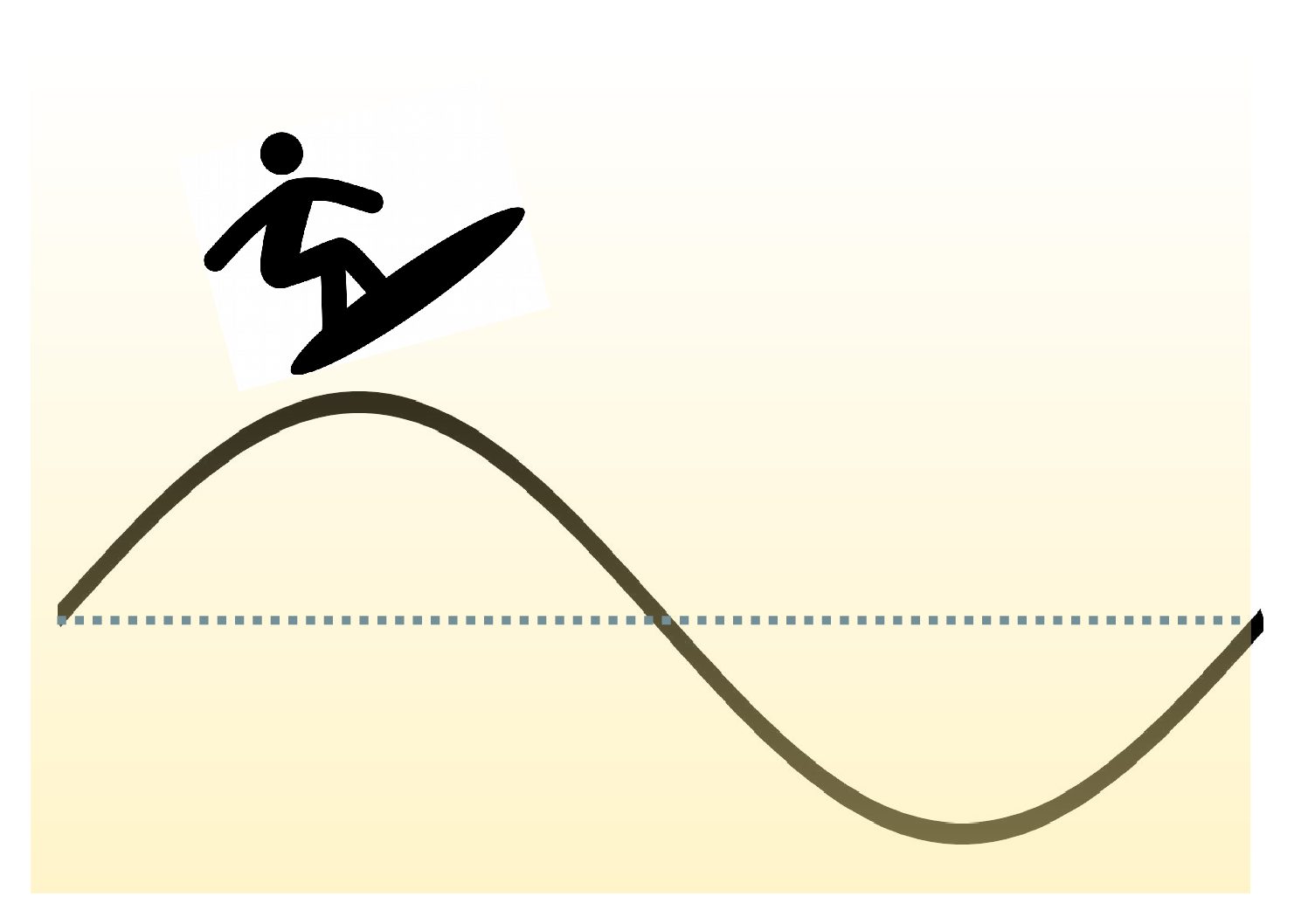がん免疫療法コラム


抗体の利用と抗体医薬品 【抗体の働き】 《Part.2》
特定の異物が体内に侵入すると、「抗体」がその異物が持つ「抗原(目印)」と特異的に結合します。そして、その異物を無力化したり、免疫細胞による攻撃を促進したりします。「抗体医薬品」は「抗体」が「抗原」と結合する性質に加え、このような「抗体」の作用を利用して効果を発揮します。「抗体医薬品」に利用されている「抗体」の作用には大きく分けて3つのパターンがあり、今回はその攻撃パターンについて見て行きたいと思います。また、それらの作用がどのように「抗体医薬品」に応用されているのかについても触れたいと思います。
■中和作用
細菌に「抗体」が結合することによって、細菌が産生する毒素が作用しないようにする、または相手がウイルスの場合には他の細胞に感染できないようにします。このように直接、相手の攻撃を無力化することを「中和作用」と呼びます。Vol.46に出て来た「抗サイトカイン療法」はこれに属します。
「がん細胞」などでは、その表面にある受容体に増殖因子(リガンド)などが結合して増殖するものがあります。「抗体」は、このリガンドと受容体の結合をブロックすることにより作用を発揮します。ブロックの方法には、リガンドに結合して受容体との結合をブロックするケースと、反対に受容体に結合してリガンドとの結合をブロックする2つのケースがあります。このような方法で「抗体」がリガンドの刺激をブロックすることにより、「がん細胞」は増殖できなくなります。
がんの増殖シグナルを阻害するような分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤などは、この「中和作用」を利用しており、標的となる分子に結合して阻害作用を発揮します。
■抗体依存性細胞障害活性
ウイルスは細胞に入り込み増殖しますが、ウイルスが入り込んだ細胞は貪食細胞が飲み込むには大きいので、貪食細胞では退治することができません。しかし、ウイルスに感染した細胞にはその細胞の表面にウイルスに特異的な「抗原」が発現しているので、この「抗原」に「抗体」が結合します。
そして、この「抗体」にNK細胞、単球、マクロファージなどが結合し、活性酸素やタンパク分解酵素を出して感染した細胞を傷害します。この働きを「抗体依存性細胞傷害活性(以下、ADCC)」と呼んでいます。多くの「抗体医薬品」はこの作用を主な薬理作用としています。
「がん細胞」においてもウイルスと同様に、「がん細胞」の表面に発現する特異的な「抗原」と「抗体医薬品」の結合がADCCを起こし、「がん細胞」を破壊します。
■補体依存性細胞障害
「補体」というタンパク質で出来た物質が「抗体」の攻撃力を増強することが知られています。細菌などの異物と「抗体」が結合すると、「補体」が次々と活性化されます。さらに、活性化された「補体」が細菌の表面で結合して、細胞上に膜侵襲〔まくしんしゅう〕複合体というドーナツ状の形を作ります。この複合体が細菌の細胞膜に小さな穴をあけて細胞を破壊します。これを「補体依存性細胞障害(以下、CDC)」と呼んでいます。
「がん細胞」に「抗体医薬品」が結合するとそこに「補体」が結合します。結合した「補体」は活性化され、「がん細胞」の表面でCDCを起こして「がん細胞」を破壊します。
以上のように「抗体医薬品」には、「抗体」の持つ「中和作用」、「補体依存性細胞障害」および「抗体依存性細胞障害活性」が利用されています。現在の「抗体医薬品」はこの作用をさらに増強したり、他の効果のある薬剤を組み合わせたりとバリエーションを増やすような試みが行われています。次回は上記で説明した作用を持つ既存の「抗体医薬品」と共に、これらの新たな試みを取り入れた「抗体医薬品」について具体的に見て行きたいと思います。
参考文献
- 一般社団法人 日本血液製剤協会ホームページ, 免疫について http://www.ketsukyo.or.jp/plasma/globulin/glo_02.html
- 斉藤幹良, 抗体の現状と新たな潮流, 日薬理誌, 147, 168-174, 2016 https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/147/3/147_168/_pdf