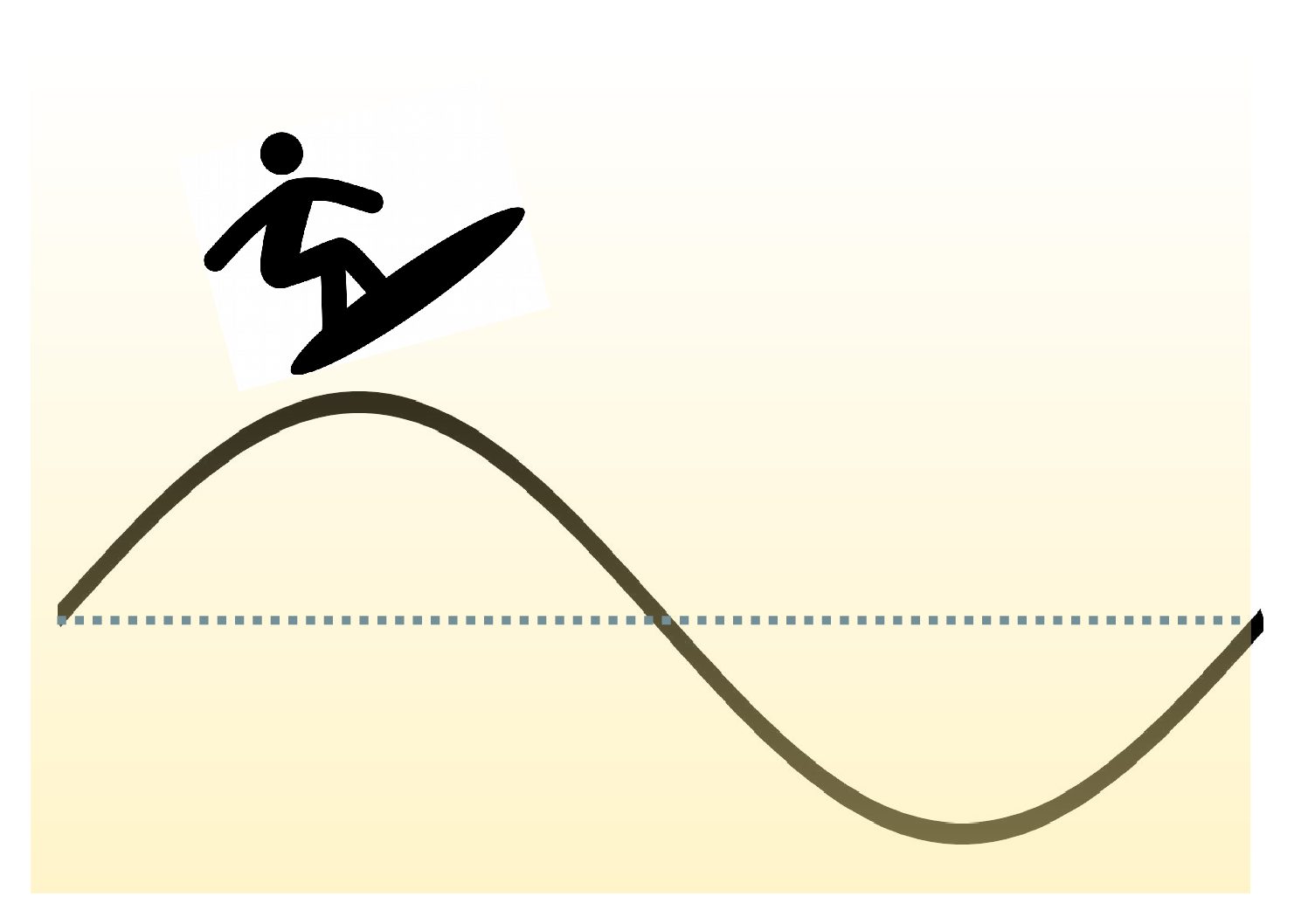がん免疫療法コラム


がん免疫療法の効果を左右する自己抗体
自己抗体とがん免疫療法の関係
がん免疫療法は、体の免疫を利用してがん細胞を攻撃する治療です。特に免疫チェックポイント阻害薬は、多くの患者さんに新しい希望をもたらしてきました。
しかし、この治療はすべての人に効くわけではありません。効果に差が出る理由の一つとして、最近「自己抗体」という体の中の抗体が注目されています。
自己抗体とは、本来は体を守るはずの免疫が、自分自身の細胞やタンパク質を攻撃してしまう抗体のことです。リウマチや膠原病など自己免疫疾患で知られていますが、がん免疫療法にも深く関わることがわかってきました。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によってブレーキをかけられた免疫を再び活性化する薬です。そこに自己抗体が関わることで、治療効果を高める場合もあれば、逆に妨げる場合もあります。
研究で明らかになったこと
アメリカの研究チームは、自己抗体と体内のタンパク質の反応性について調べるためにがん患者374名と健康者131名を対象に血液を解析しました。
その結果、がん患者のほうが自己抗体の量が高いこと、そして特定の自己抗体が免疫チェックポイント阻害薬の治療効果や予後と関係していることがわかりました。
たとえば、ウイルス増殖を抑制する働きのあるタンパク質「インターフェロン」を中和する自己抗体があると、治療効果を後押しするケースがあると報告されています。一方で、必要な免疫の働きを邪魔する自己抗体もあり、治療効果を下げてしまう可能性もあります。
自己抗体のメリットとリスク
自己抗体の存在には「良い面」と「悪い面」の両方があります。
自己抗体は、免疫の過剰反応を抑え、免疫細胞の働きを正常化させることがメリットです。自己抗体の有無が「効きやすい患者」を予測するマーカーになる可能性も考えられます。自己抗体の働きによっては、がんを攻撃するための免疫経路を妨げてしまうことがあり、副作用(免疫関連の炎症など)を強める可能性もあります。
このように、自己抗体が存在することで、メリットとデメリットが両立するために注意が必要です。
今後の展望
今回の研究は、自己抗体ががん免疫療法の効果を左右する重要な要素であることを示しました。
今後は、自己抗体を調べることでがん免疫療法の治療効果を予測する仕組みが期待されます。また、自己抗体の働きをうまく利用したり、逆に悪影響を減らす薬と組み合わせたりする治療法の開発も進むかもしれません。
自己抗体は、がん免疫療法をさらに発展させるための新しいカギです。研究が進むことで、より多くの患者さんに最適な治療を届けられる未来が期待されています。
参考URL
Carenet News「がん免疫療法の効果に自己抗体が影響か」
https://www.carenet.com/news/general/hdn/61219