がん患者様のためのお役立ちブログ


緩和ケアと余命の関係性とは?「最期の選択」ではない緩和ケアと最新治療解説
「緩和ケア」という言葉には、「余命が短い人」「最期の選択」といったイメージが持たれがちです。
しかし実際には、緩和ケアは治療の初期段階から取り入れられる医療の一つであり、末期に限ったものではありません。
むしろ、緩和ケアと最新の治療を組み合わせることで、より前向きに病気と向き合うことができ、大きな希望を見出すことも可能です。
今回の記事では、緩和ケアと余命の関係性、緩和ケアにおける誤解と真実、そして注目されている新しい治療法についてわかりやすく解説します。
【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
INDEX
緩和ケアとは

緩和ケアとは、がんなどの重い病気に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さまとご家族がより自分らしく過ごせるよう支援する医療です。
病気のどの段階でも導入でき、決して「治療の終わり」を意味するものではありません。
痛みや不安に対するケアを通じて、生活の質(QOL)を大切にした日々を支えることが緩和ケアの大きな役割です。
緩和ケア=終末期は誤解
「緩和ケア」と聞くと、「最期のときに受けるもの」「治療を諦めた後に行うケア」というイメージを持つ方も少なくありません。
しかし、それは大きな誤解です。
緩和ケアは「よりよく生きるための医療」であり、病気とともに過ごすための大切なサポートです。実際、緩和ケアはがんの診断直後から導入できる医療であり、抗がん剤治療や手術、放射線療法などの標準治療と併用することが可能です。
つらい症状や精神的な不安を和らげることで、患者さまが治療に前向きに取り組めるようサポートするのが、緩和ケアの大きな役割です。
また、緩和ケアは単に病状に対応するだけでなく、「人としての尊厳を守りながら生きること」を支える医療です。
特にがん治療は長期間にわたることが多く、副作用や精神的な負担が積み重なりやすいため、緩和ケアを早い段階から導入することで、治療の継続意欲や生活の質(QOL)の維持にも大きく貢献するとされています。
さらに、緩和ケアは患者さまご本人だけでなく、ご家族の精神的・身体的負担を軽減することも目的としています。介護や看病に伴うストレス、将来への不安に寄り添いながら、一緒に過ごす時間の質を保つサポートも行います。
国の「がん対策推進基本計画」においても、「診断時からの緩和ケアの導入」が明記されており、医療現場でも早期緩和ケアの重要性が広く認識されるようになってきました。
つまり、緩和ケアは「死を待つ医療」ではなく、「命を支える医療」です。
病気と向き合いながら、一日一日を穏やかに、自分らしく過ごすための前向きな選択肢のひとつとして、多くの患者さまに届けられるべきケアなのです。
緩和ケアの目的
緩和ケアの最大の目的は、「病気を治すこと」ではなく、患者さまとご家族がその人らしい生活を送れるよう支えることにあります。
がんなどの進行性疾患では、病気による苦痛だけでなく、治療の副作用や、病気が進行することで生じるさまざまな症状が、日々の生活に大きな影響を与えます。
緩和ケアは、それらの身体的・精神的な苦痛や負担を少しでも軽くし、心身ともに穏やかに過ごす時間を保つための医療です。
以下に、緩和ケアが具体的にどのような側面を支援するかをまとめます。
| 緩和ケアの主な目的 | 内容 |
| 身体的苦痛の緩和 | 痛み、呼吸困難、吐き気、倦怠感、食欲不振などの症状をコントロールする |
| 精神的・心理的な支援 | 不安、抑うつ、恐怖感、気分の落ち込みなどに対して寄り添い、心の安定を促す |
| 家族へのサポート | 介護や看病に伴う身体的・精神的負担を軽減し、家族の不安や悩みにも対応する |
| 社会的問題への対応 | 経済的負担、仕事との両立、在宅療養の環境整備など、生活面での課題に寄り添う |
| スピリチュアルな側面への配慮 | 人生の意味や死への恐れ、信仰に関する問題など、言葉にしづらい内面的な苦しみに対応する |
| 治療選択のサポート | 病状や希望に応じた治療の選択を、患者さま・ご家族とともに考え、支援する |
緩和ケアは、がんの進行や治療によって生じる痛みや苦痛を「我慢するもの」として放置せず、積極的に和らげることを目的とした医療です。
例えば、強い痛みによって寝たきりになっていた方が、適切な痛み止めの使用によって食事を楽しんだり家族との会話を楽しめるようになることもあります。
こうした変化は、患者さまご本人にとってもご家族にとっても、日常の尊厳や喜びを取り戻す大きな一歩となります。
さらに、緩和ケアはその人の「生き方」や「価値観」を大切にする医療でもあります。
どのような治療を希望するか、どこで最期を迎えたいかといった個々の思いや願いを丁寧に聞き取り、それに沿ったケアを行います。
このような緩和ケアは医師や看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士など多職種がチームとなって行います。
緩和ケアと余命の関係性
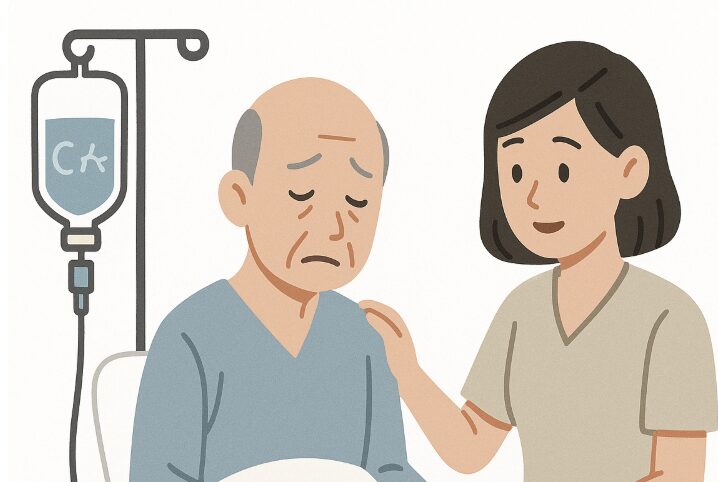
緩和ケアは「余命が残り少ない人の最期の選択」と思われがちですが、本当は「今を大切に生きるための医療」です。
緩和ケアを受けることが、「余命が短い」と決まったことを意味するわけではありません。
確かに緩和ケアは終末期の患者さまにも用いられますが、本来の役割は病気に伴う苦痛や不安を和らげ、生活の質を保つことです。
そのため病状の進行具合にかかわらず、がんと診断された早い段階から受けられる医療として推奨されています。
実際にがんの診断直後から緩和ケアを導入することで、
・症状のコントロールがしやすくなる
・気持ちが安定する
・治療への意欲が保たれる
といった効果が報告されています。
緩和ケアを早期に導入した方が、穏やかに日常を送れる時間が長く保たれるケースもあるのです。
緩和ケアでできること
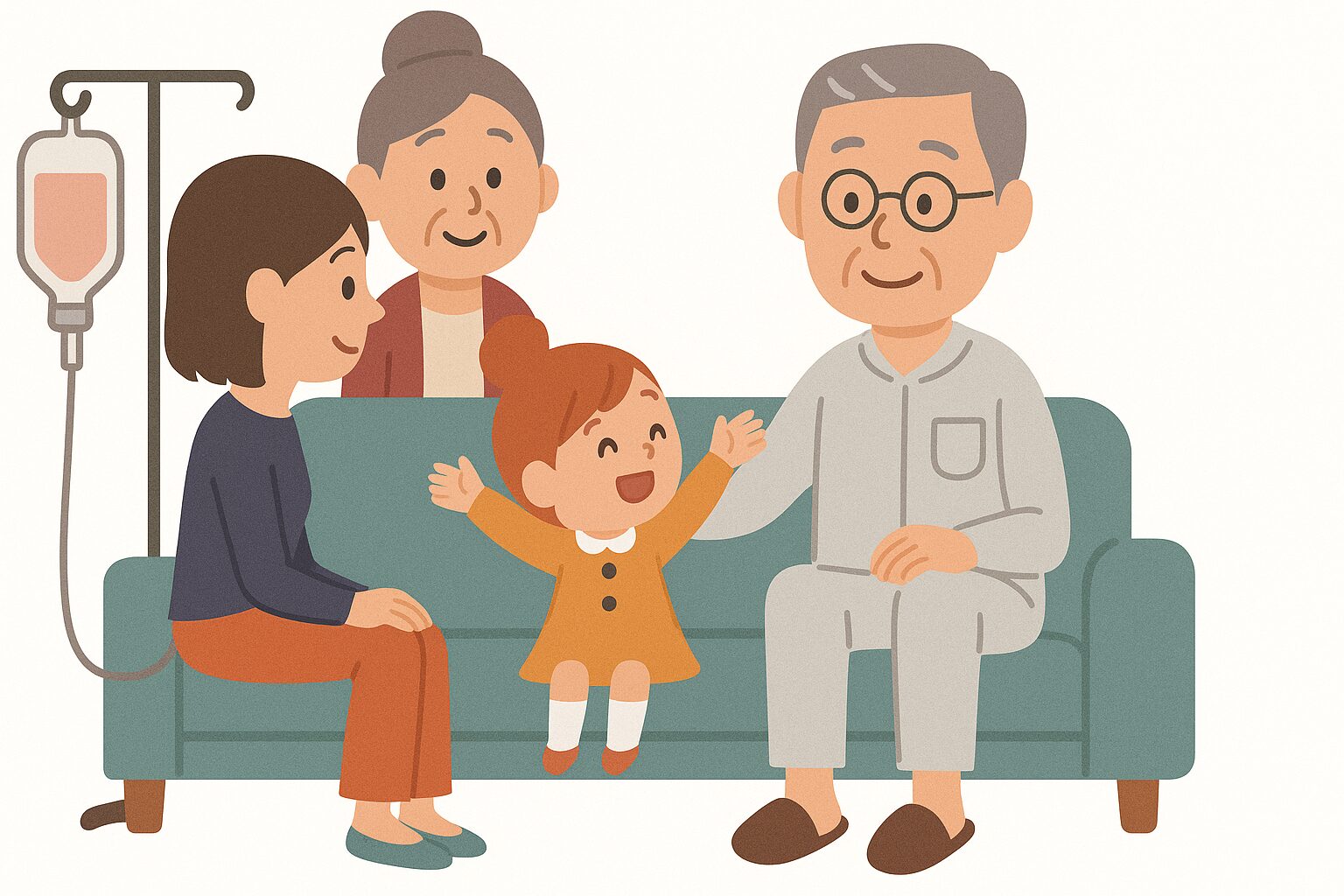
緩和ケアは、がんをはじめとする進行性疾患に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さまとご家族がより自分らしく穏やかに過ごせるよう支える医療です。
その役割は幅広く、治療中・治療後・さらには終末期まで、さまざまな場面で活用されています。
ここでは、緩和ケアで実際にどのようなサポートが行われているのか解説していきます。
症状の緩和
がんの進行や治療に伴って生じる痛み、吐き気、息苦しさ、倦怠感、食欲不振などの症状は、日常生活に大きな負担をもたらします。
緩和ケアでは、こうした症状をできるだけ早い段階で和らげることを重視しています。
たとえば、
・痛みには適切な鎮痛薬の使用や投与方法の調整
・吐き気には制吐剤の使用
など、一人ひとりの症状に合わせた対応が行われます。
症状をコントロールすることで治療を続けやすくなり、日常生活の質も保ちやすくなります。
心のケア
がんに伴う不安や恐怖、気分の落ち込みといった心理的ストレスは患者さまの生活の質に大きく影響します。
緩和ケアでは、こうした心理的ストレスに対するケアも医療の一環として重視されています。
具体的には、
・臨床心理士によるカウンセリング
・医師・看護師との定期的な対話
などを通じて、不安や孤独に寄り添う支援が行われます。
また、死への恐れや生きる意味を考えるスピリチュアルな悩みにも敬意を持って向き合い、支援が行われます。
家族への支援と在宅医療
病気の影響は患者さま本人だけでなく、ご家族にも及びます。
介護疲れや将来への不安、経済的な問題など、家族が抱える負担にも緩和ケアは対応します。
例えば、以下のような支援が提供されます。
| 支援内容 | 具体例 |
| 介護負担の軽減 | 訪問看護、ヘルパー派遣、介護用具の手配など |
| 経済・制度面の相談 | 医療費助成、介護保険制度の利用、生活支援サービスの紹介など |
| 心理的サポート | 家族向けカウンセリング、看取りに関する情報提供 |
また、患者さまが住み慣れた自宅で過ごしたいと希望する場合は、在宅緩和ケアの導入も可能です。
医師や看護師、訪問薬剤師などの多職種チームが連携し、自宅での療養を支える体制が整えられています。
ホスピスケア
人生の終末期が近づいた際には、「ホスピス」や「緩和ケア病棟」といった選択肢があります。
これらは、延命を目的とした治療よりも、痛みの緩和と安らぎを重視した医療環境です。
「できるだけ静かに、落ち着いた時間を過ごしたい」「残された時間を家族とゆっくり過ごしたい」といった思いを持つ方に適しています。
ホスピスでは、医療ケアに加え、心理的・社会的・スピリチュアルなサポートも含めて総合的なケアが提供されます。
また、ご家族が付き添える時間が確保されていることも多く、最期の時間を穏やかに過ごすことができます。
治療後の包括支援
治療が終了し経過観察に入った後でも、体調不良や再発への不安、社会復帰への戸惑いなど多くの課題が残る場合があります。
緩和ケアは、こうした治療後の不安定な時期にも寄り添える医療です。
再発リスクに対する不安や、症状の変化に対する相談窓口として、継続的に関わることで、安心して次の生活へ移行できるよう支援します。環境の整備や心理的サポートを行うのも、緩和ケアの大切な役割です。
希望を支える緩和ケア

緩和ケアは患者さまがその人らしく生きるための前向きな医療です。
たとえ病気が進行していても、「痛みが少ない時間を過ごしたい」「家族と穏やかに過ごしたい」「自分でできることを続けたい」といった、小さくても大切な希望を叶える力があります。
緩和ケアは、希望を支える医療として、以下のような視点から患者さまとご家族を支援します。
| 支援の視点 | 内容の例 |
| 自分らしさの尊重 | 好きなことを続ける、望む生活環境で過ごすなど |
| 人とのつながりの維持 | 家族との時間を大切にする、会いたい人に会う |
| 身体的・精神的な安心 | 痛みや不安を和らげ、穏やかに日々を過ごせるように支援する |
| 意思決定のサポート | 治療方針や生活の選択を自分の意思で決めるための情報と対話の提供 |
「もうできることはない」ではなく、「今できることを大切にする」こと。
それが、希望を捨てない緩和ケアの本質です。
病とともに過ごす時間も、自分らしく、安心して生きられるよう支える医療がここにあります。
緩和ケアと6種複合免疫療法
緩和ケアは、身体や心のつらさをやわらげながら、その人らしい時間を大切に過ごすための医療ですが、近年では治療と両立できる新たな医療技術との併用も注目されています。
その一つが「6種複合免疫療法」です。
これは、免疫の力を活用してがんを多角的に制御する先進的な治療法で、標準治療が難しいケースや、治療後の再発予防として導入されることもあります。
緩和ケアと併せて実施することで、生活の質(QOL)を維持だけでなく向上も見込め、がんと向き合う選択肢を広げることが期待されています。
以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








