がん患者様のためのお役立ちブログ


ゲノム医療とは? メリットデメリットとがんとの関係について解説
近年、ゲノム医療が注目を集めています。
「ゲノム医療とは何か?」
「どのような病気に活用されるのか?」
「最新の治療法やメリットは?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ゲノム医療は、人の遺伝情報(ゲノム)を解析し、それぞれの患者さまに最適な治療を選択する先進的な医療です。
特にがん治療や遺伝性疾患の診断・治療に大きな可能性をもたらしており、標準治療では対応が難しかったケースにも新たな選択肢を提供しています。
今回の記事では、ゲノム医療の基本的な仕組みから、がんや遺伝性疾患への応用、最新の治療法、メリット・課題までを詳しく解説します。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
ゲノム医療とは

ゲノム医療とは、人の遺伝情報(ゲノム)を解析し、病気の診断や治療に活かす医療を指します。
近年、特にがん治療の分野で注目されており、患者さまごとに異なる遺伝子の変化を調べることで、より効果的で個別化された治療が可能になってきました。
従来の治療が「がんの種類」や「部位」に基づいていたのに対し、ゲノム医療では「がん細胞の遺伝的特徴」に着目する点が大きな違いです。
ゲノム医療は、単に病気を見つけるだけでなく、どの薬が効くか・効かないかを事前に予測することができるため、無駄な治療を避け、患者さまにとって最適な治療法を選択する助けになります。
特に注目されているのが「がんゲノム医療」です。
がんゲノム医療は、がん細胞特有の遺伝子変異を検出し、その変異に対応する分子標的薬や免疫療法を選択する治療法です。
この技術の進歩により、一人ひとりのがんに合わせた精密な医療が可能になってきています。
ゲノム医療の仕組み
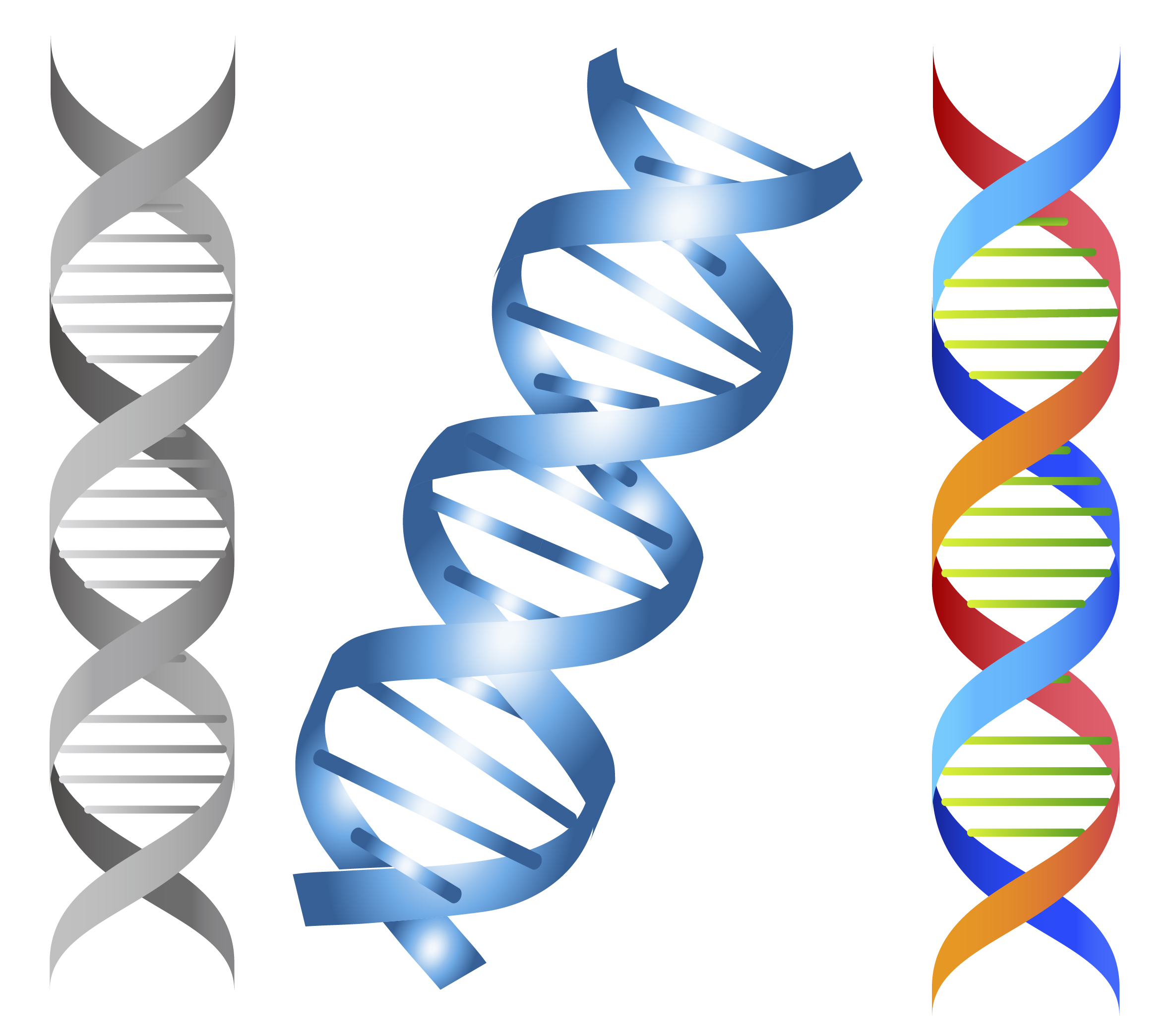
ゲノム医療は、患者さまの体から採取したがん組織や血液などのサンプルからDNAを抽出し、遺伝子情報を解析することで行われます。
中心となるのが「遺伝子パネル検査」で、これは数百種類のがん関連遺伝子を一度に調べることができ、変異の有無を確認します。
この検査によって、以下のような治療選択が可能になります。
| 分子標的薬の選定 | EGFRやHER2など、特定の遺伝子変異に応じた薬剤の使用が検討される。 |
| 免疫療法の適応判断 | PD-L1、MSI、TMBなどの指標により、免疫チェックポイント阻害薬の効果を予測。 |
| 臨床試験の候補選定 | 希少変異や治療法が確立していない場合、治験の選択肢を提示。 |
検査結果は「エキスパートパネル」と呼ばれる専門家チームによって評価され、最終的な治療方針が決定されます。
このように、ゲノム医療は解析結果をもとに科学的根拠に基づいた治療選択を行うのが特徴であり、今後の医療の中心的役割を担うとされています。
がんにおけるゲノム医療
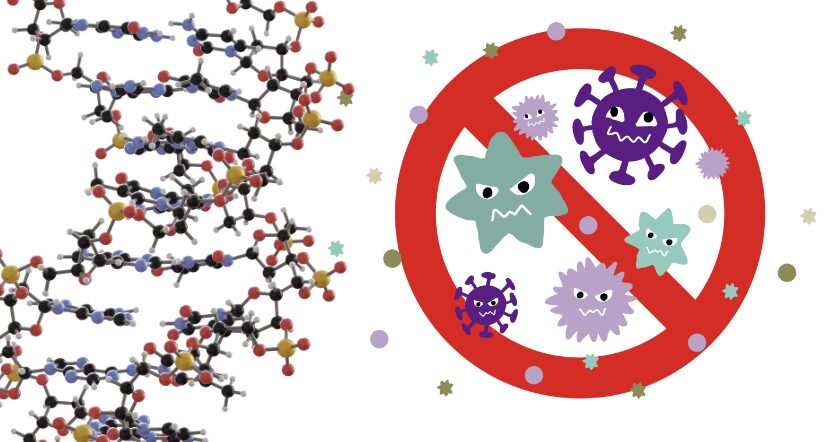
がんにおけるゲノム医療は、がん細胞に生じた遺伝子の異常を解析し、個々の患者さまに最も適した治療法を導き出すことを目的としています。
がんは遺伝子の変異によって発生する病気であるため、ゲノム情報の解析は治療法選択において非常に重要な役割を果たし、特に標準治療が効かない、もしくは適応できない進行がん患者さまに対しては、遺伝子パネル検査によって分子標的薬や免疫療法の可能性が検討されます。
ゲノム医療の一例を上げると、肺がんにおけるEGFR変異や、乳がんにおけるHER2、BRCA1/2変異などが該当します。
ゲノム情報に基づく治療は、不要な治療を避け、効果的な薬剤のみを選択できるため、副作用の軽減や生活の質(QOL)向上にもつながり、さらに検査結果からは治療薬の候補だけでなく、臨床試験への参加が提案されることもあります。
このように、がんにおけるゲノム医療は、がんの種類や特徴に合わせて、患者さま一人ひとりに最適な治療法を提供する新しい選択肢として、非常に重要な位置づけとなっています。
遺伝性疾患におけるゲノム医療
遺伝性疾患におけるゲノム医療は、特定の遺伝子に生じた異常(変異)を調べることで、病気の診断・予防・治療に役立てる医療です。
これまで診断が難しかった疾患も、遺伝子レベルで原因を特定できるようになり、早期発見や家族への情報提供が可能になっています。
代表的な例としては、BRCA1・BRCA2遺伝子の変異によって発症リスクが高まる「家族性乳がん・卵巣がん」があります。
こうした遺伝子の変異が確認されると、本人だけでなく、家族にも定期的な検診や予防的治療の選択が促されることがあります。
また、保険診療の対象として認められている遺伝性疾患の検査も増えており、2020年からはBRCA遺伝子検査(遺伝子に変異があるかどうかを調べる検査)が保険適用となりました。
希少疾患(難病)におけるゲノム医療
希少疾患や難病は、発症例が少なく原因が特定されにくいため、診断や治療に時間がかかるケースが多くあります。
こうした中で注目されているのがゲノム医療の活用です。
ゲノム医療では、患者さまの遺伝子情報を解析することで、疾患の原因となる遺伝子変異を特定し、正確な診断につなげることができます。
特に、従来の検査では異常が見つからなかった患者さまに対しても、全エクソーム解析や全ゲノム解析(いずれも遺伝情報を解析する技術)といった包括的な検査によって、原因遺伝子を発見できる可能性があります。
| ゲノム医療の活用例 | 内容 |
| 診断の確定 | 長年不明だった症状の原因が遺伝子変異であると判明するケースがある。 |
| 治療法の選択 | 特定の遺伝子変異に対して有効な治療薬の候補が見つかる場合がある。 |
| 家族への情報提供 | 遺伝の可能性がある場合、家族にも適切な対応ができる。 |
このように、ゲノム医療は希少疾患に苦しむ患者さまや家族にとって、希望となる可能性を秘めた医療です。
ゲノム医療のメリット

ゲノム医療は、患者さま一人ひとりの遺伝情報をもとに病気の診断や治療方針を決定する、いわゆる「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」の核となる存在です。
従来の医療では、がんの種類や発生部位などに基づいて治療方針が決定されてきましたが、ゲノム医療では「遺伝子の変化」や「体質の違い」に応じた、より的確な治療選択が可能になります。
特にがん領域では、分子標的薬や免疫療法との相性を事前に予測できるため、無駄な治療を回避し、効果の高い治療へと導けるのが大きな利点です。
また、難病や希少疾患では、これまで診断がつかなかったケースに対して、原因遺伝子を突き止めることで、診断確定や新たな治療の糸口が得られる可能性もあります。
| 個別に最適化された治療 | 遺伝子情報に基づいて、その人に合った薬や治療法を選択できる。 |
| 副作用の軽減 | 効果の見込めない治療を避けることで、身体への負担を抑えられる。 |
| 早期診断・予防に役立つ | 遺伝的リスクが高い場合、定期的な検診や予防的対応が可能になる。 |
| 家族への情報提供 | 遺伝性の病気であれば、家族も適切な対応を取るための参考になる。 |
また、がんゲノム医療では、治療選択だけでなく、臨床試験(治験)への参加につながる可能性もあるため、新たな治療の機会が広がる点も注目されています。
このように、ゲノム医療は単なる診断の手段ではなく、「正確な診断」「的確な治療」「将来への備え」を支える包括的な医療として、今後ますます重要性を増していくといえるでしょう。
ゲノム医療の課題

ゲノム医療は個別化医療の中核を担う先進的な取り組みとして注目されていますが、実用化に向けてはさまざまな課題も抱えています。
特に、制度面・倫理面・技術面における課題が複雑に絡み合っており、今後の発展にはこれらの問題を解決する必要があります。まず大きな課題として挙げられるのが、診療体制や人材の不足です。
遺伝子解析の結果を正確に読み取り、適切な治療方針へと導くには、専門的な知識と経験が必要です。
しかし、ゲノム医療に精通した医師や遺伝カウンセラーが全国的に不足しており、地域による医療格差が懸念されています。
また、解析結果の解釈が難しいケースも多く、「異常あり」と判明しても、実際に治療へ結びつくかどうかは別問題です。
特に、発見された遺伝子変異が「臨床的に意義があるかどうか」が不明なこともあり、患者さまへの説明や対応に慎重さが求められます。
| 人材不足 | ゲノム情報を扱える医師・遺伝カウンセラーの育成が急務。 |
| 地域格差 | 都市部と地方でゲノム医療を受けられる環境に差がある。 |
| データ解釈の難しさ | すべての遺伝子変異が治療に直結するわけではない。 |
| プライバシー・倫理の問題 | 遺伝情報の扱いや家族への説明などに関する課題も存在する。 |
個人の遺伝情報を扱うことに対する倫理的配慮やプライバシー保護も重要なテーマです。
本人だけでなく、家族の遺伝的リスクにまで関わるため、情報の取り扱い方には慎重な対応が求められます。
ゲノム医療の費用と保険適用について
ゲノム医療の中でも、がんに対する「がん遺伝子パネル検査」は2019年から保険適用となり、一定の条件を満たせば公的医療保険が適用され、3割負担で受けられます。
対象は、標準治療がない、または治療効果が期待できない進行がんの患者さまです。
| 項目 | 保険適用時の自己負担(3割) | 自由診療の場合 |
| がん遺伝子パネル検査 | 約10万〜15万円 | 約50万円前後 |
| BRCA1・BRCA2遺伝子検査(遺伝性乳がん・卵巣がん) | 約6万円 | ー |
| 全ゲノム解析 | 保険適用外 | 約100万〜200万円 |
また、高額療養費制度や医療費控除などを活用することで、自己負担を軽減することも可能です。
ただし、すべてのゲノム検査が保険適用されるわけではなく、自由診療になるケースもあるため、事前に医療機関での確認が重要です。
ゲノム医療と免疫療法
ゲノム医療は、免疫療法の適応判断や効果予測においても重要な役割を果たしています。
免疫療法は、患者さま自身の免疫力を活性化してがん細胞を攻撃する治療法ですが、すべての患者さまに有効とは限らないため、事前に効果が期待できるかを見極めることが必要です。
そこで活用されるのが、ゲノム解析による遺伝子マーカーの検出です。
例えば、以下のような情報が免疫療法の効果判定に役立ちます。
| PD-L1発現量 | 高いほど免疫チェックポイント阻害薬が効果を発揮しやすい。 |
| MSI(マイクロサテライト不安定性) | 高値であれば免疫療法が有効な可能性が高い。 |
| TMB(腫瘍変異負荷) | 遺伝子変異が多いほど免疫の反応が高まりやすい。 |
このように、ゲノム医療は免疫療法と密接に関わっており、両者を組み合わせることで高い治療効果が期待されるケースも少なくありません。
特に近年は、複数のアプローチを組み合わせた「6種複合免疫療法」に注目が集まっており、次の項目ではその内容について詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








