がん患者様のためのお役立ちブログ


がん性腹膜炎とは? 腹膜播種との違いや原因、治療法について解説
腹腔内を覆う薄い膜である腹膜をがん細胞が破って広がる「腹膜播種」が進行することで、がん性腹膜炎を引き起こします。
がん性腹膜炎は、胃がんや大腸がん、卵巣がんなどの消化器系・婦人科系のがんで特に発生しやすいとされています。
治療には化学療法や腹水管理、免疫療法 などが選択肢となり、患者さまの全身状態に応じて適切な治療が検討されます。
今回の記事では、がん性腹膜炎の原因や症状、診断方法、治療法について詳しく解説します。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
がん性腹膜炎とは
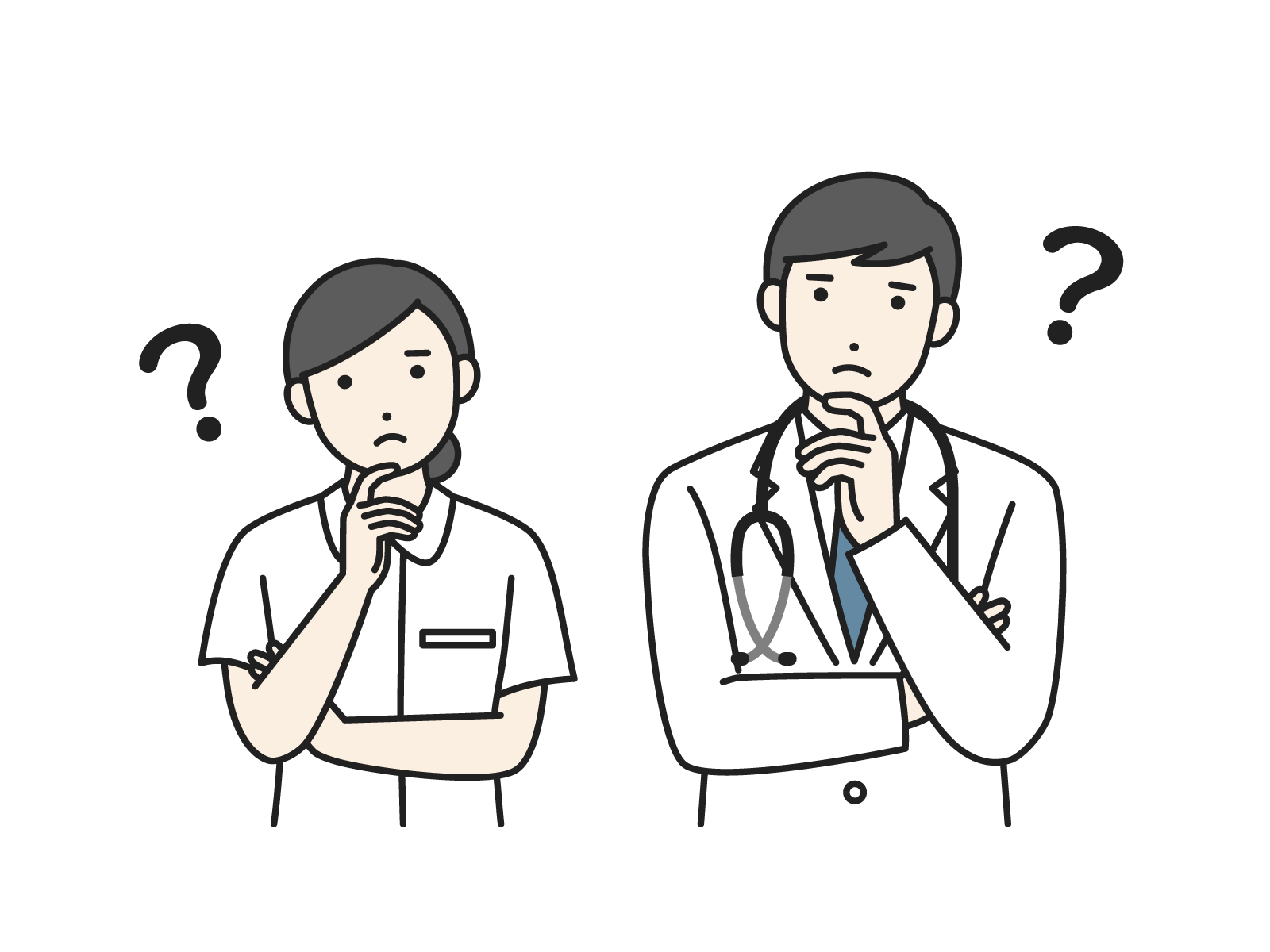
がん性腹膜炎は、「腹膜播種」が進行することで引き起こされます。
腹膜は内臓を覆う薄い膜で、消化管の動きを滑らかにする役割を持っています。
進行がんの影響でがん細胞が腹膜に散らばると、炎症や異常な液体の分泌が生じ、腹水がたまります。
がん性腹膜炎と腹膜播種との違い
腹膜播種が進行し、以下のような違いが見られる場合にがん性腹膜炎と診断される傾向にあります。
| 項目 | 腹膜播種 | がん性腹膜炎 |
| 定義 | がん細胞が腹膜に散らばる現象 | 腹膜播種が進行し、炎症や腹水貯留を伴う状態 |
| 主な症状 | 明確な症状がないこともある | 腹水貯留、腹部膨満感、食欲不振など |
| 診断方法 | 画像検査や腹腔内洗浄細胞診 | 画像検査、腹水検査、症状の確認 |
腹膜播種の段階では明確な症状が出にくいですが、がん性腹膜炎へ進行すると腹水の貯留などにより体調の変化が現れます。
がん性腹膜炎の原因
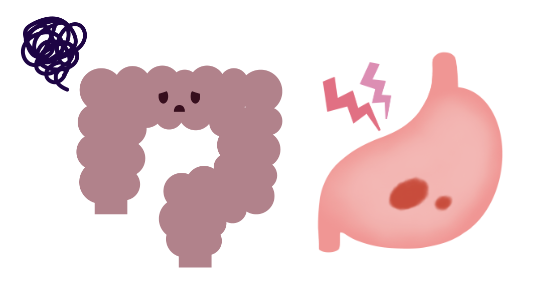
がん性腹膜炎は、腹膜播種が進行することで引き起こされます。
特に腹腔内に近い臓器のがんは腹膜播種を起こしやすく、その結果としてがん性腹膜炎へと進行する傾向があります。
がん性腹膜炎を引き起こしやすいがんは、以下のようながんが挙げられます。
- 胃がん
- 大腸がん
- 卵巣がん
- 膵臓がん
- 子宮がん(特に子宮体がん)
がんの腹膜への到達経路
これらのがんが腹膜に到達する経路は主に三つあります。
第一に、がんが直接腹膜に浸潤するケースです。例えば胃がんや卵巣がんが進行すると、がん細胞が周囲の腹膜に広がることがあります。
第二に、血流やリンパの流れに乗ってがん細胞が運ばれ、腹膜に転移する場合です。
第三に、消化管や卵巣にできたがんが、腹腔内に剥がれ落ち、腹膜のあちこちに広がる播種(はしゅ)と呼ばれる現象が起こることもあります。
がん性腹膜炎の診断
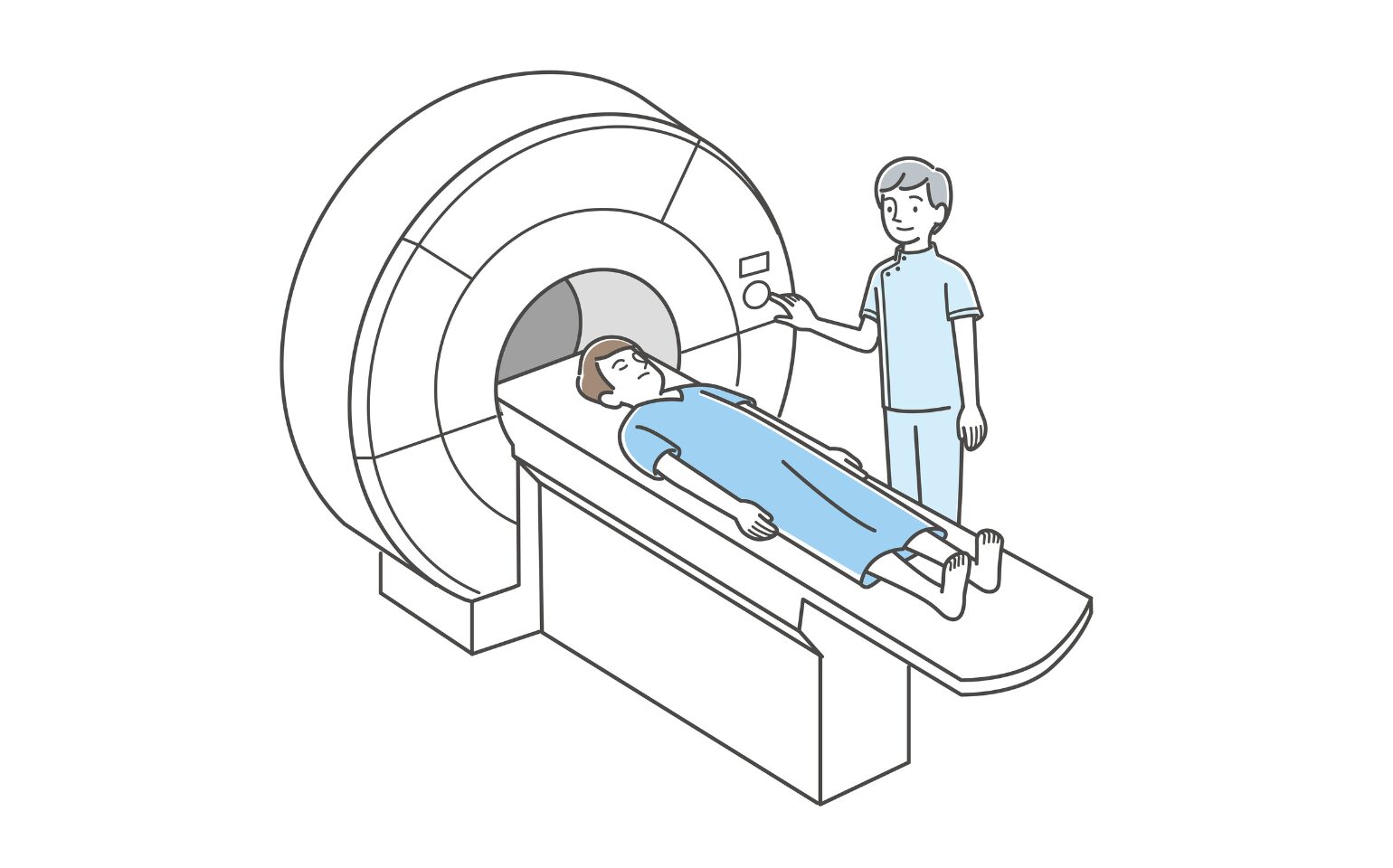
がん性腹膜炎の診断には、画像検査(CT検査・MRI検査など)や腹腔内の直接的な観察、腹水の分析などが用いられます。
がん細胞が腹膜に広がると炎症や腹水の貯留が起こりますが、初期の段階では症状が乏しいこともあるため、正確な診断ができるよう段階に応じて適した検査が行われます。
CTスキャン・MRI
画像検査は腹膜の異常や腹水の貯留、がんの広がりを詳しく調べるのに効果的なため、がん性腹膜炎の診断に広く用いられます。
CTスキャンは、X線を用いた断層撮影によって体内の構造を詳しく映し出します。
造影剤を使用すると、腹膜の肥厚や腹水の存在、がんがどの程度広がっているかがより明確にわかります。
また、他の臓器への転移も同時に確認できるため、病状の進行度を把握するのに有効です。
MRIは、磁気を利用して体内の軟部組織を鮮明に映し出します。CTと比べて腹膜の状態をより詳しく観察できるため、がん性腹膜炎の早期発見に役立つことがあります。
ただし、検査時間が長く、動きに敏感であるため、患者さまの状態によってはCTが優先されることもあります。
腹腔鏡検査
腹腔鏡検査は、腹部に小さな穴を開け、そこから内視鏡(腹腔鏡)を挿入し、直接腹膜の状態を観察する検査です。
この検査の主な特徴は以下のとおりです。
- 直接観察が可能:腹膜の肥厚やがんの広がりを目で確認できるため、より正確な診断が可能
- 組織の採取(生検):腹膜の一部を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べることで確定診断ができる
- 腹水の評価:腹水の量や性質を観察し、必要に応じて検査のために採取する
CTやMRIでは判別が難しい早期の腹膜転移も確認できるため、がん性腹膜炎の診断精度を高める重要な検査です。
腹水検査
腹水検査は、腹水がたまっている場合に細い針を腹部に挿入して腹水を採取し、成分を分析することで診断の手がかりを得る検査です。
主な検査内容は以下のとおりです。
- 細胞診:腹水中にがん細胞が含まれているかを顕微鏡で確認
- 生化学検査:腹水のタンパク質濃度や乳酸脱水素酵素(LDH)などを測定し、性質を評価
- 細菌培養検査:細菌感染が疑われる場合、培養して感染の有無を調べる
細胞診でがん細胞が検出されれば、がん性腹膜炎の確定診断につながります。
腹水中にがん細胞が見つからないこともあり、他の検査と組み合わせて総合的に診断するための材料となります。
がん性腹膜炎の治療法

がん性腹膜炎の治療は、症状の進行度や患者さまの全身状態に応じて選択されます。
主な治療法には、抗がん剤を用いる化学療法、腹水の貯留による不快な症状を軽減する腹水の管理、一部の症例で検討される手術、そして患者さまの生活の質を維持するための支持療法があります。
化学療法
抗がん剤を用いることで、がん細胞の増殖を抑え、症状の進行を遅らせることを目的とします。
主な化学療法の方法には以下のようなものがあります。
- 全身化学療法:静脈内に抗がん剤を投与し、全身に作用させる方法。標準的ながん治療の一環として行われる。
- 腹腔内化学療法:抗がん剤を直接腹腔内に注入し、腹膜に広がるがん細胞に集中的に作用させる方法。腹水の減少が期待できる。
- 分子標的治療:がん細胞の特定の分子に作用する薬を使用し、副作用を抑えながら治療を行う方法。
化学療法では副作用の管理が重要で、支持療法と組み合わせて治療を進めることが求められます。
腹水の管理
がん性腹膜炎では、腹水の貯留によって腹部膨満感や食欲不振、呼吸困難などの症状が生じることがあります。
そのため、症状を和らげる目的で腹水の管理が行われます。
腹水管理の主な方法は以下のとおりです。
- 利尿剤の使用:尿の排出を促し、腹水の貯留を抑える
- 腹水穿刺(腹水ドレナージ):針を用いて直接腹水を排出し、症状を緩和する
- 腹水濾過濃縮再静注法(CART):腹水を一度体外に取り出し、不要な成分を除去して体内に戻す方法
- 食事療法:塩分を控え、栄養バランスを考慮した食事をとる
一時的に症状が軽減しても、がんの進行によって再び腹水がたまることがあるため継続的なケアが必要になります。
手術
がん性腹膜炎に対する手術は、主に症状の緩和やがんの進行を抑える目的で行われます。
主な手術の種類は以下のとおりです。
- 腹膜切除術:がんが広がった腹膜の一部を切除し、がん細胞の負担を軽減
- 消化管バイパス手術:腸閉塞のリスクが高い場合、腸の流れを確保するために別の経路を作る
- シャント手術:腹水が多い場合、体内の別の部位に流す管を設置し、貯留を軽減
手術はがんの広がりや患者さまの体力を考慮して選択され、化学療法や支持療法と組み合わせて行われる傾向が多く見られます。
支持療法
支持療法は、患者さまの生活の質を維持し、症状を和らげることを目的としたケアの総称です。
がんの進行に伴うさまざまな不調を軽減し、できるだけ快適に過ごせるように支援します。
主な支持療法には以下のようなものがあります。
- 痛みの管理:鎮痛剤や神経ブロックを用いて痛みを和らげる
- 栄養管理:食事の工夫や栄養補助食品の活用、点滴による補給
- 精神的サポート:患者さまや家族の不安を軽減するための心理的ケア
- 緩和ケア:ホスピスや在宅医療を活用し、患者さまの希望に沿った療養環境を整える
支持療法は、治療の効果を高めるだけでなく、患者さまの心身の負担を軽減する重要な役割を果たします。
がん性腹膜炎と免疫療法
がん性腹膜炎の治療では、免疫療法が新たな選択肢として注目されています。
免疫療法は、体の免疫機能を活性化させ、がん細胞を攻撃しやすくする治療法です。
従来の化学療法や放射線療法とは異なり、副作用が比較的少ないとされ、長期的な治療が可能な場合もあります。
主な免疫療法の種類には以下のようなものがあります。
- 免疫チェックポイント阻害薬:がん細胞が免疫細胞の働きを抑える仕組みを解除し、攻撃しやすくする
- がんワクチン療法:がん細胞に特異的に反応する免疫を活性化させる
- サイトカイン療法:免疫細胞の働きを高めるタンパク質を投与し、がんに対する免疫反応を強化
近年、免疫療法の研究が進み、より高い治療効果が目指されています。その一つの治療法が6種複合免疫療法です。
6種複合免疫療法は、私たちの体の中にある免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻し、がんと闘う力を増強させる療法です。
以下、免疫療法の中で特に注目の6種複合免疫療法について詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








