がん患者様のためのお役立ちブログ


原発不明がんとは? 症状や診断、治療法について解説
もし、がんが見つかったのに、どこから発生したのかわからないと言われたら、どう感じるでしょうか。
原発不明がんは、がんの発生部位が不明であるため患者さまやご家族に、大きな不安をもたらします。
通常、がんは発生した臓器が診断名となりますが、原発不明がんは転移しているにもかかわらず、発生源が特定できません。
近年、遺伝子検査や免疫療法の進歩により、新たな検査方法や治療法が広がりつつありますが、依然として解明すべき点が多いがんの一つとされています。
今回の記事では、原発不明がんの診断から治療について、詳しく解説していきます。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
原発不明がんとは
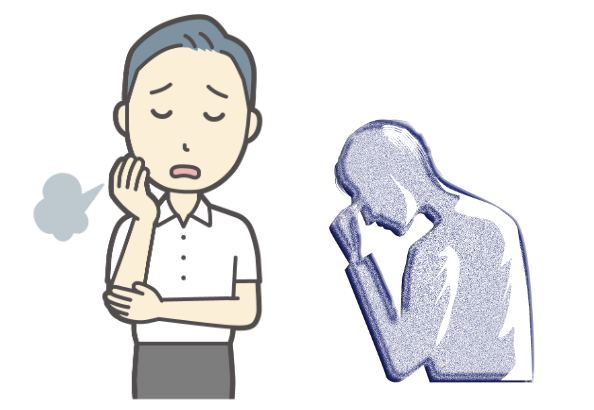
原発不明がん(CUP:Cancer of Unknown Primary)は、転移がんが見つかっているにもかかわらず、がんが最初に発生した部位(原発巣)が特定できないがんのことを指します。
一般的ながんは、原発巣が明確であるため、診断や治療方針を決定しやすいですが、原発不明がんはその特定が困難なため、診断や治療に課題が多い病気とされています。
また、発生頻度は全がんの3~5%程度で、肺や肝臓、リンパ節など、さまざまな部位に転移しやすい傾向があります。
原発不明がんの主な特徴
- 原発巣が特定できないまま転移が見つかる
- 診断が難しく、確定診断に時間がかかる
- 転移先の臓器によって症状が異なる
- 遺伝子検査や免疫組織化学検査を活用し、治療方針を決定する
近年の医療技術の進歩により、遺伝子解析を活用した診断や新たな治療法の研究が進んでいます。
その結果、病気の原発が特定できない場合でも、適切な治療方針を決定できるようになり、患者にとってより多様な治療の選択肢が提供されるようになっています。
原発不明がんの原因

原発不明がんの正確な発生メカニズムはまだ明らかになっていません。
しかし、原発不明がんでは原発巣が特定できないものの、がん細胞の遺伝子変異や異常なシグナル伝達が確認されており、こうした分子レベルの異常が病気の進行に影響を与えている可能性が指摘されています。
本来、私たちの体には異常な細胞を排除する仕組みが備わっていますが、何らかの要因でこの仕組みが破綻し、がん細胞が増殖・転移していきます。
原発不明がんでは、以下のような要因が関与している可能性があります。
| 免疫機能の低下 | がん細胞を排除する免疫の働きが弱まり転移が起こるが、一方で原発巣は免疫により消失する場合がある。 |
| がん細胞の急速な転移 | 原発巣が小さいまま急速に転移し、転移先でのみ増殖するため発見が困難になる。 |
| 細胞の異常な性質 | 原発巣の細胞が特定の臓器にとどまらず、転移先での増殖能力が高くなる。 |
| 診断技術の限界 | 現在の医療技術では、微小ながんの原発巣を発見できないケースがある。 |
こうした要因が複雑に絡み合い、原発不明がんとして診断されると考えられています。
原発不明がんの種類
原発不明がん(CUP)は、発生した原発巣が特定できないまま転移して発見されるがんですが、その中でも特定の種類のがんが含まれることが多いとされています。
原発不明がんの診断には病理検査や遺伝子検査が用いられ、組織の特徴をもとに「がんの種類」が分類されます。
原発不明がんには、以下のような種類が含まれることが多いです。
| 腺がん(腺癌) | 最も多く、約60%を占める。消化器系や肺、乳腺などの腺組織由来と考えられる。 |
| 扁平上皮がん | 皮膚や粘膜の表面細胞ががん化したもの。首のリンパ節転移として見つかることが多い。 |
| 未分化がん | 細胞の分化が不明確で、どの組織由来か特定が難しいがん。増殖が速い傾向がある。 |
| 神経内分泌がん | 神経内分泌細胞から発生するがん。ホルモンを分泌する性質を持つ。 |
| 肉腫(サルコーマ) | 骨や軟部組織から発生するまれながんで、原発不明がんとして見つかることがある。 |
原発不明がんはこれらの種類に分類されることが多いものの、転移先の特徴や遺伝子解析の結果をもとに、より詳細な診断が行われます。
原発不明がんの診断方法
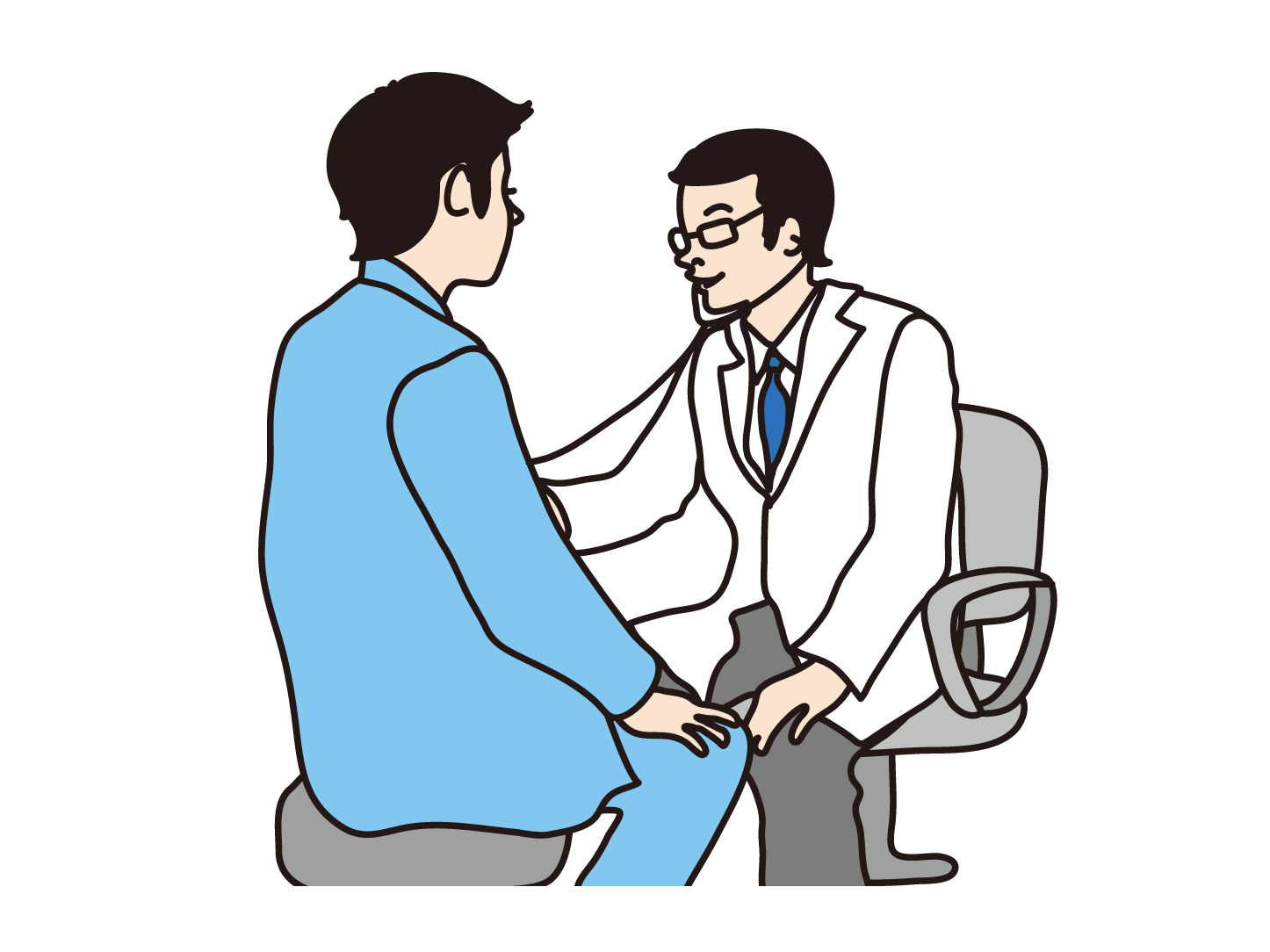
原発不明がんの診断では、転移がんの組織や細胞の特徴を詳しく調べることで、原発巣の推定を行います。
主に病理検査や画像検査に加え、免疫組織化学検査や遺伝子検査を組み合わせて診断を進めます。
以下、それぞれの検査方法について詳しく解説します。
病理検査
病理検査は、原発不明がんの診断において最も重要な検査の一つです。
転移がんの組織を採取し、顕微鏡で観察することで、がん細胞の種類や性質を詳しく分析します。
この検査によって、がんの組織型を特定し、原発巣の推定につなげることが可能です。
しかし、病理検査の結果だけでは原発巣を完全に特定することは難しいため、免疫組織化学検査や遺伝子検査と組み合わせて診断を進めます。
画像検査
画像検査は、原発不明がんの診断において原発巣を特定したり、転移の広がりを評価したりするために重要な検査です。
体内の異常な腫瘍を可視化し、がんの分布や特徴を把握することで、治療方針を決定する際の参考になります。
| 検査方法 | 特徴 |
| CT(コンピュータ断層撮影) | 胸部や腹部の詳細な断層画像を取得し、肺や肝臓、リンパ節転移の有無を確認する。 |
| MRI(磁気共鳴画像) | 頭部や骨、軟部組織の詳細な画像を得るのに適しており、脳転移や骨転移の評価に用いられる。 |
| PET-CT(陽電子放射断層撮影) | がん細胞の代謝活性を利用し、全身の転移巣を探索する。特に原発巣の特定に有効な場合がある。 |
| 超音波検査(エコー) | 肝臓やリンパ節の病変をリアルタイムで観察し、細胞診や組織採取の際のガイドとして活用される。 |
画像検査によって、肺がん・胃がん・乳がん・膵がん・大腸がんなど、さまざまな原発巣の可能性を絞り込むことができます。
免疫組織化学検査
免疫組織化学検査は、がん細胞の表面に発現する特定のタンパク質を調べることで、がんの種類や原発巣の推定を行う検査です。
病理検査の一部として実施され、組織切片に特異的な抗体を反応させ、がん細胞の性質を詳細に分析します。
特定のマーカーが陽性または陰性であるかを確認することで、がんの組織型や原発臓器の可能性を絞り込むことができます。
| マーカー | 主な適応がん |
| TTF-1(甲状腺転写因子-1) | 肺がん、甲状腺がん |
| CEA(癌胎児性抗原) | 消化器系がん(大腸がん・胃がん・膵がんなど) |
| ER(エストロゲン受容体)・PR(プロゲステロン受容体) | 乳がん |
| PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺がん |
| CDX2 | 大腸がん、胃がん |
| CK7(サイトケラチン7)・CK20(サイトケラチン20) | 泌尿器系や消化器系のがんの鑑別に使用 |
免疫組織化学検査は、病理検査と組み合わせることで、原発不明がんの正確な診断を助ける重要な手法です。
ただし、原発巣を完全に特定できるとは限らないため、画像検査や後述の遺伝子検査と併用して診断を進めることが一般的です。
遺伝子検査
遺伝子検査は、がん細胞のDNAやRNAを解析し、特定の遺伝子変異や発現パターンを調べることで、原発巣の特定や治療方針の決定に役立つ検査です。
原発不明がんの診断では、病理検査や免疫組織化学検査だけでは判別が難しい場合に、遺伝子検査を併用することで、より正確な診断が可能になります。
| 遺伝子マーカー | 関連するがんの種類 |
| EGFR(上皮成長因子受容体)変異 | 肺がん |
| KRAS変異 | 大腸がん、膵がん、肺がん |
| BRAF変異 | 甲状腺がん、悪性黒色腫、大腸がん |
| HER2増幅 | 乳がん、胃がん |
| TP53変異 | 多くのがん種に共通 |
| BRCA1/2変異 | 乳がん、卵巣がん |
近年では、次世代シーケンサー(NGS)を用いた包括的な遺伝子パネル検査が普及しつつあり、原発不明がんにおいても、がんの遺伝子情報をもとに最適な治療薬を選択するプレシジョン・メディシン(精密医療)が注目されています。
遺伝子検査の発展により、従来の検査では診断が困難だったケースでも、有効な治療法が見つかる可能性が高まっています。
原発不明がんの主な症状
原発不明がんの症状は、がんが転移した部位によって異なります。
初期の段階では自覚症状がほとんどないことも多く、進行後にはリンパ節の腫れや呼吸困難、腹水、骨の痛みなど、転移先の臓器に応じた症状が現れるのが特徴です。
以下に、転移の部位ごとに見られる主な症状について詳しく解説します。
リンパ節転移による症状
原発不明がんでは、リンパ節転移が多く見られ、特に首や脇の下、鼠径部(足の付け根)などのリンパ節が腫れることで発見されることがあります。
リンパ節転移が進行すると、しこりが目立つようになり、痛みや圧迫感を伴う場合もあります。
リンパ節の腫れが持続し、感染症の兆候がない場合は、がんの可能性を考慮し、精密検査が必要です。
主な症状
- 首や脇の下、足の付け根のリンパ節が腫れる(しこりができる)
- 腫れたリンパ節に痛みが生じることがある
- リンパ節が大きくなり、圧迫による違和感や神経痛が現れることがある
リンパ節転移の診断には、触診や超音波検査(エコー)、CTやPET-CTなどの画像検査が用いられます。
また、病理検査や免疫組織化学検査によって、転移がんの性質を詳しく調べ、原発巣の特定を試みます。
胸膜・腹膜転移による症状
原発不明がんが胸膜や腹膜に転移すると、体内の臓器を包む膜の間に胸水(きょうすい)や腹水(ふくすい)が異常に溜まり、さまざまな症状を引き起こします。
これにより、肺や消化器の働きが妨げられ、呼吸困難や腹部膨満感といった症状が現れることが多くなります。
主な症状
- 胸膜転移の場合
- 息苦しさ(呼吸困難)
- 胸の痛みや圧迫感
- 長引く咳や痰の増加
- 腹膜転移の場合
- 腹部の張りや膨満感
- 食欲不振や消化不良
- 吐き気・嘔吐
- 便秘や腹痛
胸膜・腹膜転移の診断には、CTや超音波検査(エコー)、胸水・腹水の細胞診が用いられます。
症状が進行すると生活の質(QOL)を大きく損なうため、胸水や腹水を排出する処置や対症療法が重要になります。
肺転移・肝転移による症状
原発不明がんが肺や肝臓に転移すると、それぞれの臓器の機能が低下し、特有の症状が現れます。
肺転移では呼吸に関わる症状、肝転移では消化や代謝機能に影響を与える症状が多く見られます。
これらの転移は進行するまで自覚症状がないことも多く、診断時にはすでに広範囲に広がっているケースもあります。
主な症状
- 肺転移
- 長引く咳や血痰(けったん)
- 息切れや呼吸困難
- 胸の痛み
- 発熱や倦怠感
- 肝転移
- 腹部の張りや右上腹部の痛み
- 食欲不振や体重減少
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 倦怠感や吐き気
肺転移や肝転移の診断にはCTやMRI、PET-CTなどの画像検査が用いられ、肝転移の場合は血液検査(肝機能検査)も重要です。
骨転移による症状
原発不明がんが骨に転移すると、骨の破壊や骨密度の低下が進み、痛みや骨折のリスクが高まります。骨は血流が豊富なため、がん細胞が転移しやすい部位の一つです。
特に脊椎、骨盤、大腿骨、肋骨などに転移が起こりやすく、神経圧迫による痛みや運動障害を引き起こすことがあります。
主な症状
- 骨の痛み(特に夜間や安静時に悪化しやすい)
- 骨折のリスク増加(軽い衝撃でも骨折することがある)
- 脊髄圧迫による神経症状(しびれ、麻痺、排尿・排便障害)
- 高カルシウム血症(倦怠感、吐き気、意識障害の原因となる)
骨転移の診断にはX線、CT、MRI、骨シンチグラフィーなどの画像検査が用いられます。
また、血液検査でカルシウム値や腫瘍マーカーを測定することもあります。
治療には放射線治療や骨吸収抑制薬(ビスホスホネート、デノスマブ)を用い、痛みの緩和や骨折予防を行います。進行すると運動機能が低下するため、リハビリや緩和ケアも重要となります。
原発不明がんとステージ(病期)の関係
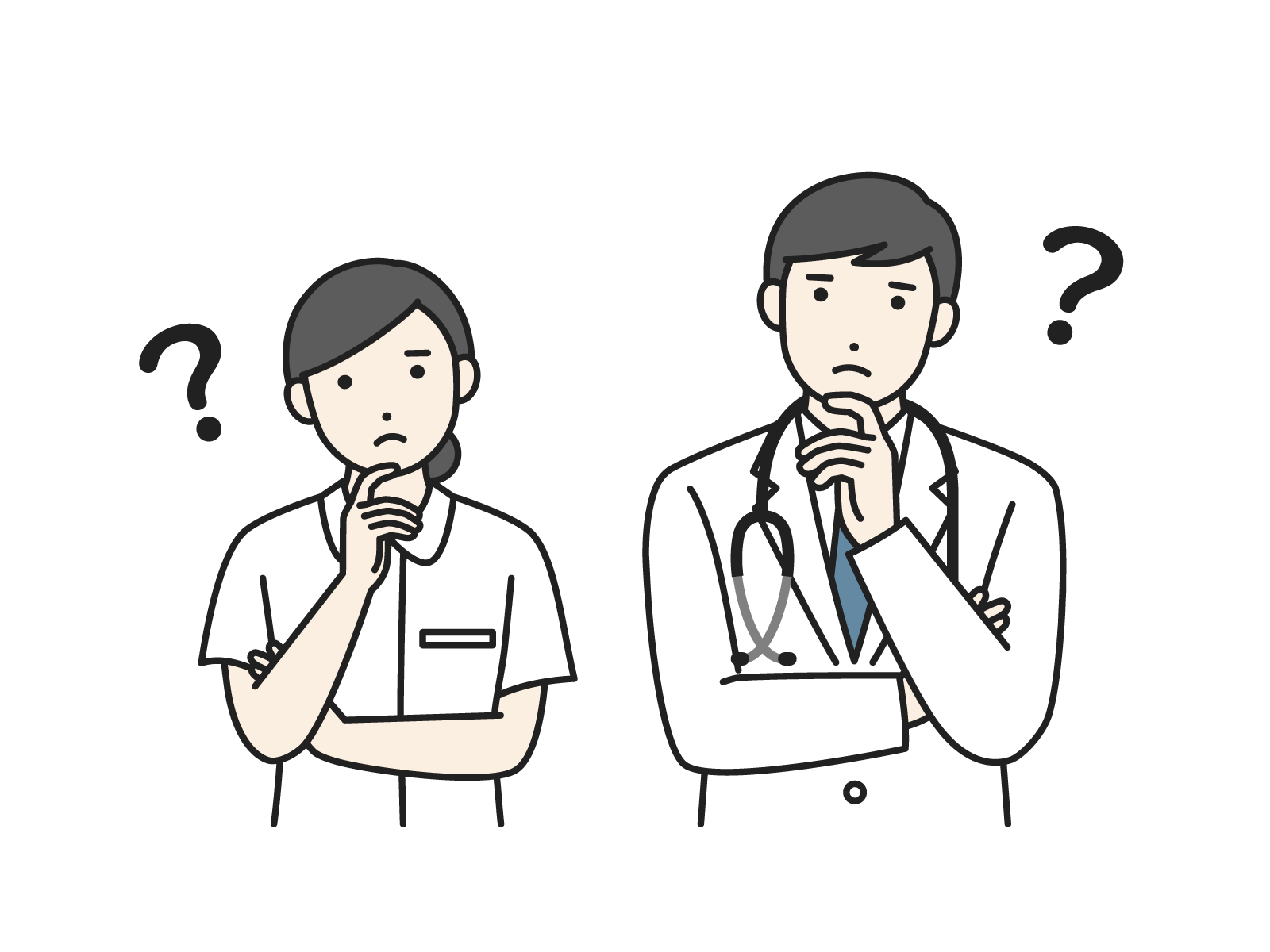
原発不明がんは、がんの原発巣が特定できないまま転移した状態で発見されます。そのため、ステージの概念はありません。ただし多くの場合、遠隔転移がある状態のステージ4と同等の判断をすることがあります。
原発不明がんの病期の特徴
- 診断時に複数の転移巣が確認されることが多い
- 原発巣が小さすぎる、または消失しているため特定が難しい
- 進行度に応じた標準的なステージ分類が適用されない
- 治療方針は転移の部位や組織型に基づいて決定される
一般的ながんのステージ分類では、ステージⅠ~Ⅲは局所進行がん、ステージⅣは遠隔転移がある進行がんとされます。
しかし、原発不明がんでは前述の通り、発見時にすでに転移しているため、ステージ4と同等の判断となります。
原発不明がんの再発
原発不明がんは、診断時点ですでに転移しているため、治療後も再発のリスクが高いとされています。
再発は初回治療で消失したがん細胞が再び増殖するケースや、新たな転移巣が発見されるケースなどがあり、経過観察が非常に重要になります。
原発不明がんの再発に関する特徴
- 原発巣が特定されていないため、再発部位の予測が難しい
- 化学療法や放射線治療でいったん縮小しても、一定期間後に再発することがある
- 再発後は、がんの性質が変化し、治療に対する反応が変わる可能性がある
- 免疫療法や分子標的治療を含めた新しい治療法が適用されることもある
再発が疑われる場合には、定期的な画像検査(CT、MRI、PET-CTなど)や腫瘍マーカーの測定が行われます。
原発不明がんの治療法

原発不明がんの治療は、転移したがんの組織型や広がり、患者さまの全身状態を考慮して決定されます。
原発巣が特定できないため、一般的ながんの治療とは異なり、転移がんとしての治療が中心となります。
| 治療法 | 特徴 |
| 化学療法 | 抗がん剤を用いた全身治療。がんの種類に応じた標準療法が選択される。 |
| 分子標的治療 | がん細胞の特定の遺伝子変異を狙った治療で、効果が期待できる場合がある。 |
| 免疫療法 | 免疫チェックポイント阻害剤などを用い、がん細胞への攻撃を促進する。 |
| 放射線治療 | 症状の緩和や局所制御を目的に行われる。 |
| 外科手術 | 転移が限られている場合、切除が検討されることもある。 |
近年では、遺伝子検査による個別化治療が進み、原発巣が不明な場合でも効果的な治療を選択できる可能性が広がっています。
また、免疫療法の研究が進み、より高い治療効果が目指されています。その一つの治療法が6種複合免疫療法です。
6種複合免疫療法は、がん免疫療法の1つで、私たちの体の中にある免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻し、がんと闘う力を増強させる療法です。
以下、免疫療法の中で特に注目の6種複合免疫療法について詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








