がん患者様のためのお役立ちブログ


がんの完全寛解とは?完治や完全奏効との違い、寛解後の治療法まで詳しく解説
がんの治療経過を語るうえで、「完全寛解」という言葉は重要な意味を持ちます。
完全寛解とは、検査や診察でがんが確認できない状態に達した状態を指します。完治とは異なり、今後の再発リスクがゼロになったわけではありません。
特にステージ4のように進行したがんにおいては、完全寛解を目指す治療も複雑化し、患者さまご本人やご家族にとって治療方針の理解がより重要になります。
今回の記事では、「完全寛解」とは何かという基礎的な知識から、「完治」「完全奏効」との違い、寛解に至るまでの期間、そして寛解後の治療法まで、幅広く解説します。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
がんの完全寛解とは
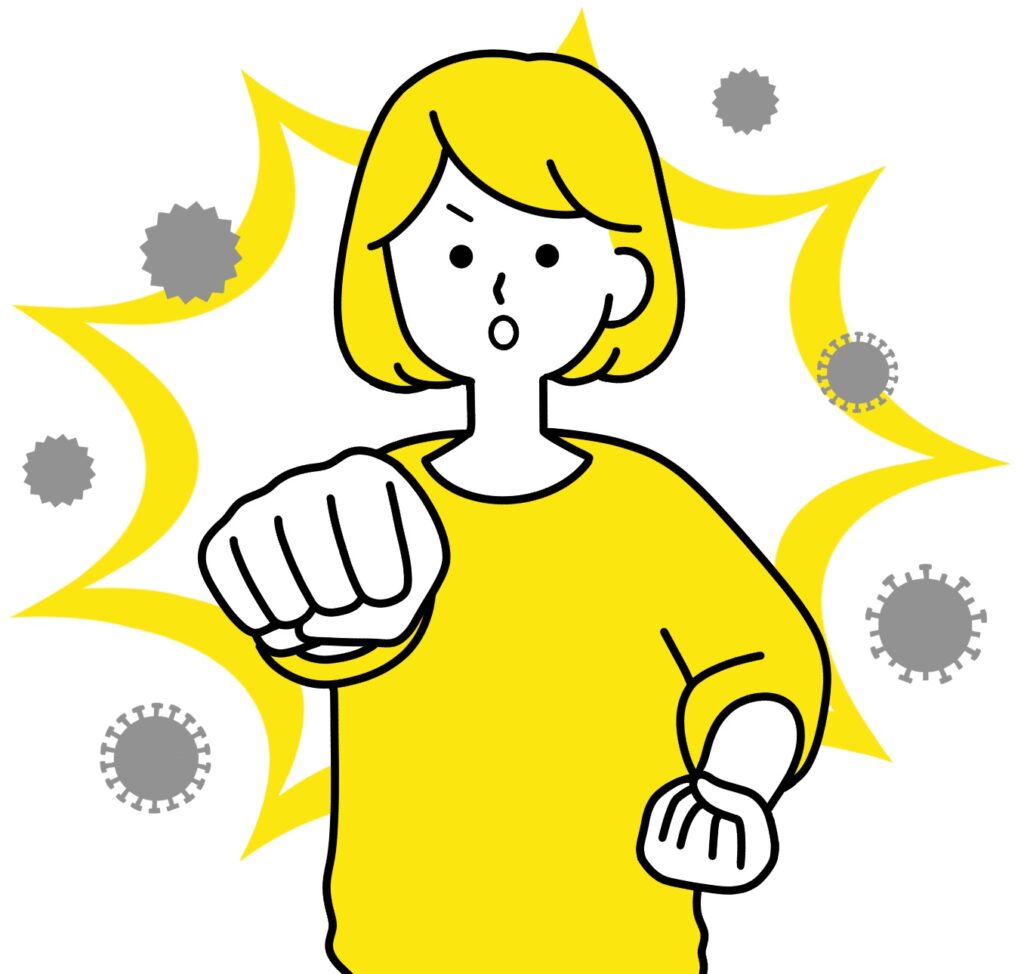
がんの完全寛解とは、検査や診察でがんが確認できない状態に達したことを指します。
治療により目に見える腫瘍が消失した場合に使われますが、体内に微小ながん細胞が残っている可能性も否定できないため、「完治」とは区別されます。あくまで治療効果のひとつの指標とされています。
完全寛解と完治の違い
がん治療において「完全寛解」と「完治」は似た言葉に見えますが、意味は異なります。
完全寛解は、微小ながん細胞が残っている可能性があり、再発のリスクが完全には消えたわけではありません。
一方、完治とは、医学的にがんが完全に消失し、再発のリスクが極めて低いと考えられる状態を指します。
両者の違いをまとめると、次のようになります。
| 項目 | 完全寛解 | 完治 |
| 定義 | 検査でがんが確認できない状態 | 医学的にがんが完全に消失した状態 |
| リスク | 再発の可能性あり | 再発の可能性が極めて低い |
| 時期 | 治療中または治療後間もない段階でも判断される | 長期間再発しないことを確認して判断される |
完全寛解の段階でも、完治に向けて治療や経過観察を続けることが大切です。
完全寛解と完全奏効の違い
「完全寛解」と「完全奏効」も似た表現ですが、意味に違いがあります。
完全寛解は、診察や画像検査などでがんの存在が確認できない状態を指します。
一方、完全奏効は、治療効果判定の専門用語で、投与した薬剤や治療により、画像上の腫瘍が完全に消失した場合に使われます。
どちらもがんが見えなくなった状態を示しますが、評価するタイミングや方法に違いがあります。
違いをまとめると、次のようになります。
| 項目 | 完全寛解 | 完全奏効 |
| 意味 | がんが検査で確認できない状態 | 薬剤や治療によって腫瘍が完全に消失した状態 |
| 評価方法 | 画像検査・診察・血液検査など総合的に判断 | 主に画像検査により判断 |
| 使用場面 | 治療効果全体の評価 | 治療薬や治療法ごとの効果判定 |
完全寛解も完全奏効も、がん治療の道のりの中で、大きな希望となる指標といえるでしょう。
がんが完全寛解する期間
がんが完全寛解に至るまでの期間は、がんの種類や進行度、選択される治療法、さらには患者さま一人ひとりの体質によっても大きく異なります。
一般的には、抗がん剤治療や放射線療法、免疫療法などを数カ月単位で継続したのち、経過観察を経て完全寛解と判断されるケースが多く見られます。
ただし、治療効果が現れるスピードもさまざまで、治療開始後数カ月という比較的短期間で効果が現れる場合もあれば、年単位での長い経過観察を必要とする場合もあります。
例えば、血液がんでは比較的早期に寛解が確認されることもありますが、固形がんの場合は時間をかけて段階的に効果を見極めていくことが一般的で、より長い時間がかかる傾向があります。
ステージ4のがんが寛解する確率
ステージ4のがんは、多くの場合で転移を伴い、がん細胞が複数の部位に広がっているため、完全寛解に至る確率は一般的には高くないとされています。
しかし、近年の医療技術の進歩により、ステージ4から完全寛解に至る例も少しずつ報告されるようになってきました。
例えば、化学療法や放射線療法に加えて、患者さまの免疫細胞を活用する「6種複合免疫療法」のような新しい治療アプローチを組み合わせることで、従来よりも良好な経過をたどるケースが増えています。
たとえ完全寛解には至らなくとも、がんの進行を長期間抑え、日常生活を無理なく続けられることも少なくありません。
がんの完全寛解の診断

がんの完全寛解は、単一の検査結果だけで判断されるものではなく、複数の検査を通じて慎重に総合評価が行われます。
完全寛解とは、検査上、がん細胞が確認できない状態を指しますが、微小ながん細胞が体内に残存している可能性も否定できないため、診断には高い精度が求められます。
一般的に、完全寛解の診断には以下のような検査が行われます。
| 検査項目 | 内容 |
| 画像検査 | CT、MRI、PETなどの画像診断で、腫瘍の有無や縮小状態を詳しく確認します。 |
| 血液検査 | 血液中の腫瘍マーカーの値や、全身の状態を反映する各種指標を測定します。 |
| 身体診察 | 問診に加え、視診や触診を通じて、身体全体の状態や異常の有無を確認します。 |
| 必要に応じた組織検査 | がん細胞の残存をより正確に把握するため、組織サンプルを採取して検査することもあります。 |
これらの結果を総合的に判断し、がんの兆候がまったく認められないと判断された場合に、「完全寛解」と診断されます。
ただし、前述したように、検査で異常が見られなくても、体内に目に見えない微小ながん細胞が潜んでいる可能性は否定できません。
そのため、完全寛解と診断された後も、定期的な検査による経過観察が不可欠です。
万が一、再発の兆候が見られた場合でも、早期に対応できる体制を整えておくことが、安心して日常生活を送るための大切な支えになります。
がん完全寛解後の治療
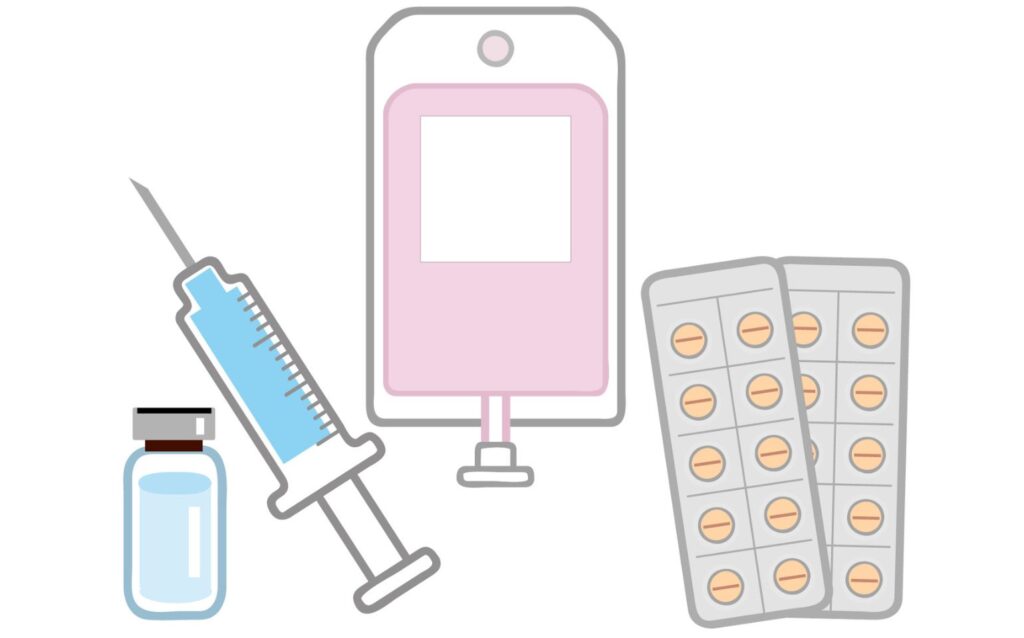
がんが完全寛解に至った後も、再発を防ぎ、より安定した状態を目指すために治療が続けられることがあります。
例えば、化学療法や分子標的薬、免疫療法などを組み合わせながら、患者さま一人ひとりの体調に合わせて、経過を見守りながら治療を進めていきます。
一方、再発リスクが低いと考えられる場合や、治療による負担が大きいと判断される場合には、積極的な治療は行わず、定期的な検査による経過観察が選択されることがあります。
化学療法(抗がん剤治療)
完全寛解後も、がん細胞の再増殖を防ぐ目的で化学療法が継続されることがあります。このような治療は「地固め療法」や「維持療法」とも呼ばれ、目に見えない微小ながん細胞に働きかけることで、再発のリスクを抑える効果が期待されます。
ただし、抗がん剤は副作用を伴う場合もあるため、患者さまの体調や生活状況を踏まえながら、無理のない治療計画を立てるのが一般的です。
この治療の目的は二つあり、一つはがんの再発を可能な限り防ぐこと、そしてもう一つは、患者さまが安心して、充実した日常生活を送れるよう支援することです。
分子標的薬
分子標的薬は、がん細胞特有の異常なタンパク質や遺伝子変異を狙い撃ちする治療法です。従来の抗がん剤に比べ、正常な細胞への影響をできるだけ抑えながら効果を発揮できる点が特徴です。
完全寛解後も、再発予防のために特定の分子標的薬を継続使用するケースがあります。
副作用が少ないとは限らないため、体調管理や定期的な検査が欠かせませんが、より個別化された治療により、生活の質を維持しながら治療を続ける選択肢が広がっています。
免疫療法
免疫療法は、患者さま自身の免疫機能を高め、がん細胞を排除する力をサポートする治療法です。
近年では、「免疫チェックポイント阻害薬」などの新しい治療薬が登場し、がんに対する新たなアプローチとして注目されています。
これらの治療は、がん細胞による免疫の抑制を解除し、自然な免疫反応を引き出すことを目指します。完全寛解後も、体内に潜んでいるかもしれない微小ながん細胞を抑える目的で、免疫療法が取り入れられることがあります。
体への負担が比較的少ない治療が多く、治療を続けながら日常生活を長く維持することを目指します。免疫療法は、日々進歩を続ける新しい治療分野として期待されています。
がん完全寛解と6種複合免疫療法
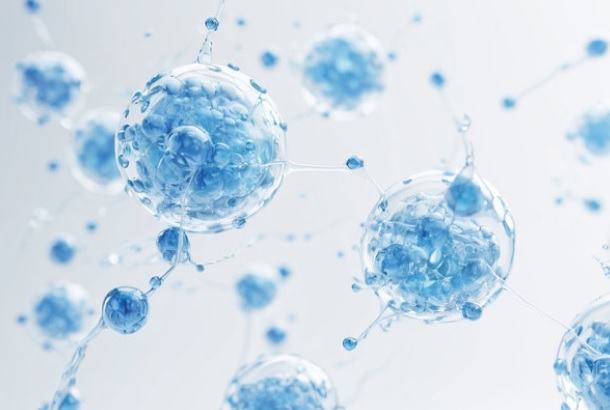
がんが完全寛解に至った場合でも、体内に微小ながん細胞が残っている可能性はゼロではありません。そのため、再発を防ぐためには継続的な取り組みが重要です。
その手段の一つとして、近年注目されているのが「6種複合免疫療法」です。
この治療法は、患者さま自身の免疫力を最大限に引き出し、6種類の異なる免疫細胞を組み合わせて多角的にがん細胞を制御することを目指しています。
体への負担を抑えながら、がんの再増殖を防ぐ新たなアプローチとして期待が高まっています。
6種複合免疫療法
6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。
6種類の免疫細胞は以下のとおりです。
- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。
- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。
- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。
- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。
- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。
- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。
これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。
6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。
6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。
また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。
副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








