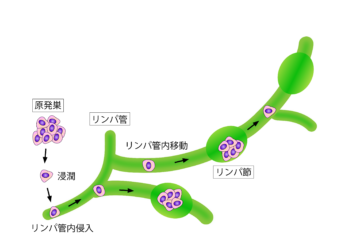がん患者様のためのお役立ちブログ


がんの抗体療法とは?副作用や免疫療法との違いについて解説
がんの治療法は多岐にわたっており、その一環として近年ではさまざまな新しい治療法が登場しています。
その新しい治療法の中でも、がん細胞を標的にした「抗体療法」は、特定の分子を狙い撃ちすることで、副作用を抑えながら効果的にがんを攻撃する方法として注目を集めています。
今回は、がんの抗体療法の基本的な仕組みとその種類について詳しく解説していきます。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
がんの抗体療法とは?
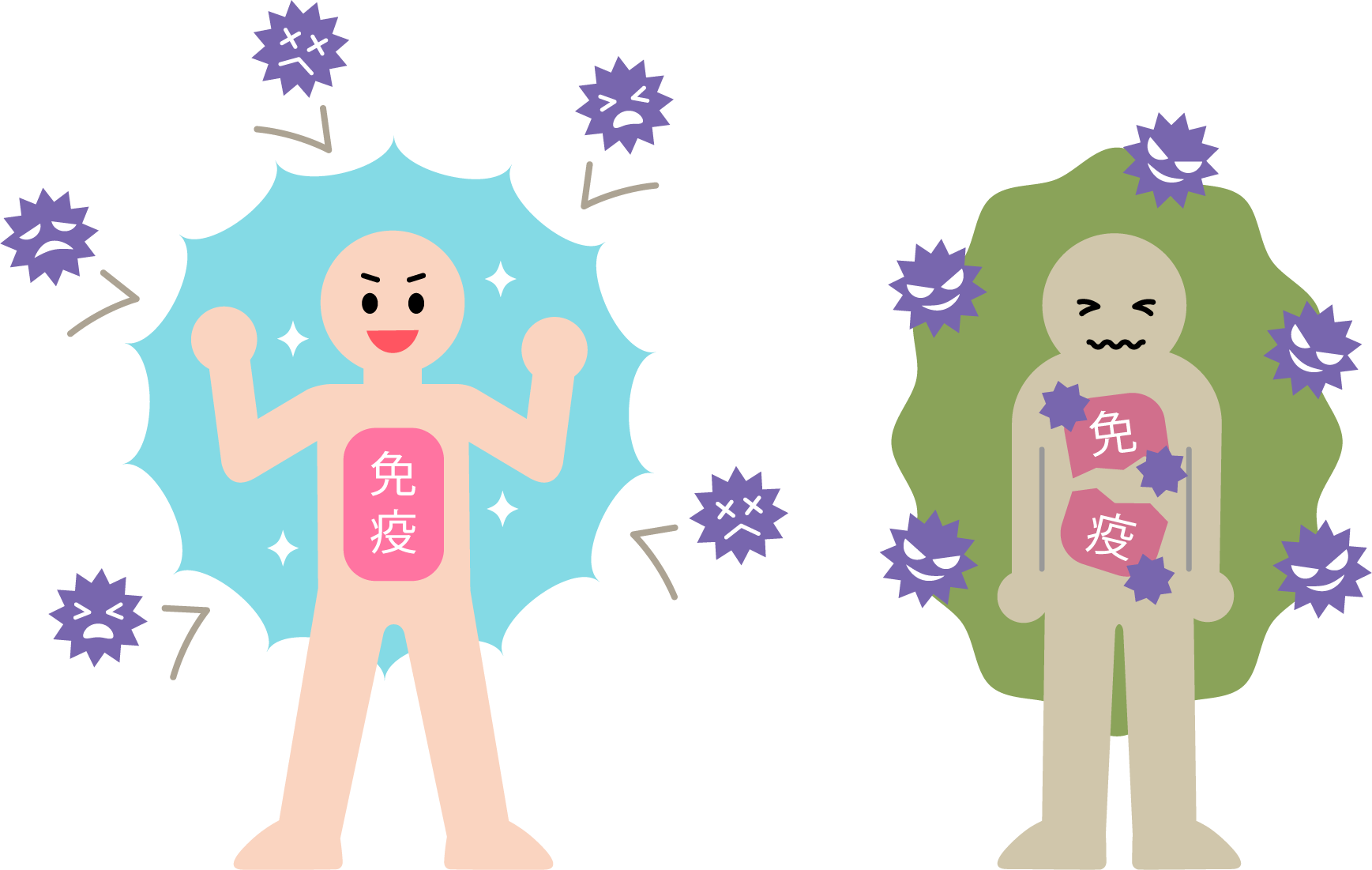
がんの抗体療法とは、がん細胞の特定の分子(抗原)を標的とするモノクローナル抗体を用いた治療法です。
抗体ががん細胞に結合することで、がん細胞の成長を抑制したり、免疫細胞ががん細胞を攻撃しやすくしたりする効果が期待されます。
この治療法は、従来の化学療法と比べて正常な細胞への影響が少なく、副作用を抑えながら治療を進められるのが特徴です。
現在では、乳がん・大腸がん・肺がん・血液がんなど、さまざまながん種に対して抗体医薬が開発・使用されています。
さらに近年では、免疫チェックポイント阻害剤や抗体薬物複合体(ADC)などの新しいタイプの抗体療法も登場し、治療の選択肢が広がっています。
抗体療法の種類
がんの抗体療法には、がん細胞の特定の分子を標的とする「モノクローナル抗体療法」以外にも、抗体に抗がん剤を結合させた「抗体薬物複合体(ADC)」、免疫細胞の働きを活性化させる「免疫チェックポイント阻害薬」など、さまざまな種類があります。
モノクローナル抗体療法
モノクローナル抗体療法は、がん細胞の特定の抗原(分子)を標的とする、人工的に作られた抗体を用いた治療法です。
この抗体は、がん細胞に特異的に結合し、がんの増殖を抑えたり、免疫細胞ががん細胞を攻撃しやすくしたりする働きを持ちます。
モノクローナル抗体療法には、以下のような作用があります。
- がん細胞の成長を阻害
増殖に関与する受容体をブロックし、がんの成長を抑制する
- 免疫細胞の攻撃を促進
抗体ががん細胞に結合し、免疫細胞ががんを攻撃しやすくする
- 血管新生を阻害
がん細胞が栄養を得るための新しい血管の形成を防ぐ
代表的なモノクローナル抗体薬
| 薬剤名(商品名) | 適応がん種 |
| トラスツズマブ(ハーセプチン) | 乳がん、胃がん |
| ベバシズマブ(アバスチン) | 大腸がん、肺がん、卵巣がん、乳がん など |
| リツキシマブ(リツキサン) | B細胞性リンパ腫、白血病 |
| セツキシマブ(アービタックス) | 大腸がん、頭頸部がん |
メリット
- ターゲットが明確なため、正常細胞への影響が少なく、副作用が比較的少ない
- 免疫機能を利用してがん細胞を攻撃できるため、従来の化学療法より効果的なケースが多い
課題
- がん細胞が耐性を持つ可能性があり、治療効果が低下することがある
- 遺伝子検査などを行い、適切な患者さまを選定する必要がある
モノクローナル抗体療法は、標的治療としての効果が期待される一方で、適応患者さまの選定が重要な治療法です。
抗体薬物複合体
抗体薬物複合体(ADC:Antibody-Drug Conjugate)は、がん細胞を標的とするモノクローナル抗体に、強力な抗がん剤(細胞障害性薬剤)を結合させた治療法です。
この治療法の最大の特徴は、正常な細胞への影響を最小限に抑えつつ、がん細胞に集中的に薬剤を届けることができる点にあります。
作用メカニズム
- モノクローナル抗体が、がん細胞の特定の分子(抗原)に結合
- がん細胞が抗体を取り込み、内部で薬剤が放出される
- 細胞内で抗がん剤が作用し、がん細胞を死滅させる
代表的な抗体薬物複合体(ADC)
| 薬剤名(商品名) | 適応がん種 |
| トラスツズマブ エムタンシン(カドサイラ) | 乳がん |
| エンホルツマブ ベドチン(パドセブ) | 尿路上皮がん |
| ポラツズマブ ベドチン | 悪性リンパ腫 |
| サシツズマブ ゴビテカン(トロデルヴィ) | トリプルネガティブ乳がん |
メリット
- がん細胞にピンポイントで抗がん剤を届けることで、副作用を軽減できる
- 化学療法単独では治療が難しいがんにも有効
課題
- 標的分子が特定のがんにしか存在しないため、適応範囲が限られる
- がん細胞が薬剤耐性を獲得する可能性がある
抗体薬物複合体(ADC)は、従来の化学療法と比べて、がん細胞を選択的に攻撃できるため、副作用を抑えながら高い治療効果を期待できる治療法です。
免疫チェックポイント阻害薬
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫から逃れる仕組み(チェックポイント機構)を解除し、免疫細胞(T細胞)ががん細胞を攻撃しやすくする治療法です。
通常、T細胞は異常な細胞を攻撃する役割を担っています。
しかし、がん細胞は「PD-L1」や「CTLA-4」などの分子を利用し、T細胞の働きを抑制することで生存することが知られています。
免疫チェックポイント阻害薬は、この抑制を解除し、免疫細胞の攻撃力を回復させることで、がん細胞を排除します。
代表的な免疫チェックポイント阻害薬
| 薬剤名(商品名) | 適応がん種 |
| ニボルマブ(オプジーボ) | 非小細胞肺がん、胃がん、腎細胞がん、悪性黒色腫 など |
| ペムブロリズマブ(キイトルーダ) | 乳がん、大腸がん、食道がん など |
| アベルマブ(バベンチオ) | 尿路上皮がん など |
| イピリムマブ(ヤーボイ) | 悪性黒色腫、腎細胞がん など |
メリット
- 自己免疫を活性化し、長期的ながん抑制効果が期待できる
- がんの種類を問わず、一部の遺伝子変異(MSI-Hなど)を持つがんにも有効
- 従来の化学療法が効かない患者さまに対する新たな選択肢となる
課題
- 免疫の過剰な活性化による副作用(自己免疫疾患のような症状:間質性肺炎、甲状腺炎など)が発生する可能性がある
免疫チェックポイント阻害薬は、がん治療の新たな柱となる治療法であり、特に進行がんや再発がんの治療成績向上に貢献しています。
抗体療法のメリット

抗体療法は、がん細胞の特定の分子を標的とすることで、高い治療効果を発揮しながら副作用を抑えられる画期的な治療法です。
従来の化学療法と比較して、以下のようなメリットがあります。
がん細胞を選択的に攻撃できる
モノクローナル抗体や抗体薬物複合体(ADC)は、がん細胞特有の分子をターゲットにするため、正常な細胞への影響を最小限に抑えることができます。
これにより、副作用を軽減しながら治療効果を向上させることが可能です。
長期的な治療効果が期待できる
免疫チェックポイント阻害薬などの一部の抗体療法は、免疫細胞を活性化することで、がんの進行を長期間抑える効果があります。
進行がんであっても、病状をコントロールしながら長期間の生存が可能となるケースが増えています。
化学療法との併用で相乗効果を発揮
抗体療法は、化学療法や放射線療法と併用することで、治療効果をさらに高めることができます。
特にHER2陽性乳がんや大腸がんでは、分子標的薬(抗体療法)と化学療法の併用により、治療成績が大幅に向上しています。
さまざまながん種に適用可能
近年の研究により、乳がん・大腸がん・肺がん・血液がんなど、多くのがん種で抗体療法が有効であることが確認されています。
さらに、新たな標的分子の発見が進み、治療の選択肢が広がっています。
抗体療法のデメリット
抗体療法は、がん細胞を特異的に攻撃できる画期的な治療法ですが、いくつかのデメリットも存在します。
治療を受ける際には、効果とリスクを十分に理解し、適切な管理を行うことが重要です。
適応が限られる
抗体療法は、特定の分子を標的とするため、すべてのがん患者さまに適用できるわけではありません。
がん細胞に標的となる分子が存在しない場合、治療効果が期待できず、事前に遺伝子検査やバイオマーカー検査が必要となります。
治療費が高額
抗体療法は、先進的なバイオ医薬品を使用するため、治療費が高額になる傾向があります。
健康保険が適用されるケースもありますが、一部の薬剤は自由診療となるため、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
効果が持続しないことがある
一部のがん細胞は、抗体療法に対する耐性を獲得することがあり、時間とともに効果が低下する場合があります。
そのため、耐性が生じた場合は、別の治療法への切り替えや、他の抗体療法との併用が必要となることがあります。
免疫関連の副作用がある
特に免疫チェックポイント阻害薬を使用する場合、免疫の過剰反応により自己免疫疾患のような副作用が発生することがあります。
代表的な副作用には、以下のようなものがあります。
- 間質性肺炎(呼吸困難、せき)
- 甲状腺炎(ホルモン異常による倦怠感、体重変化)
- 大腸炎(腹痛、下痢、血便)
症状が重篤な場合には治療を中断することもあります。
抗体療法の副作用と注意点
抗体療法は、がん細胞を特異的に攻撃するため、従来の化学療法と比べて副作用が少ない傾向があります。
しかし、薬剤の種類や患者さまの体質によってはさまざまな副作用が発生する可能性があるため、適切な管理が重要です。
主な副作用
| 副作用の種類 | 特徴と注意点 |
| インフュージョンリアクション(輸注反応) | 投与後に発熱、寒気、血圧低下などが起こることがある。特に初回投与時に注意が必要。 |
| 皮膚症状 | 発疹、かゆみ、乾燥肌が発生することがある(EGFR阻害薬など)。重症化すると皮膚炎や爪の異常が生じる場合も。 |
| 消化器症状 | 下痢・吐き気・食欲不振が見られることがある(特に抗体薬物複合体(ADC)で起こりやすい)。 |
| 免疫関連副作用 | 免疫チェックポイント阻害薬では、間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能障害などが発生することがある。自己免疫疾患に似た症状が現れるため、早期の対処が必要。 |
| 血管新生阻害薬の副作用 | 出血リスクの上昇、高血圧、創傷治癒の遅れ(ベバシズマブなど)。手術を受ける場合は事前の投与中断が必要。 |
副作用対策と注意点
- 定期的な血液検査や画像診断を行い、副作用の兆候を早期に発見する。
- インフュージョンリアクション(輸注反応)が懸念される場合は、投与前に抗アレルギー薬やステロイドを使用することが推奨される。
- 免疫関連の副作用(間質性肺炎、大腸炎など)は、重篤化する前に適切な治療(ステロイド投与など)を行う。
- 高血圧や消化器症状に対しては、生活習慣の見直しとともに、必要に応じて降圧剤や消化器系の薬剤を併用する。
- 皮膚症状が悪化した場合は、保湿や外用薬の使用、適切なスキンケアが重要。
- 出血や創傷治癒の遅れが懸念される場合は、手術前後の投与スケジュールを慎重に調整する。
抗体療法はどんな人に適している?
抗体療法の適応の可否は、がんの種類や分子の発現状況、患者さまの健康状態などを総合的に判断して決定されます。
以下の条件に該当する患者さまは、抗体療法の効果を得やすいと考えられます。
- 標的分子が確認されているがん患者さま
例として、HER2陽性乳がん、EGFR陽性肺がん、CD20陽性リンパ腫などが挙げられます。
これらのがんでは、特定の分子を標的とした抗体療法が有効です。
- 化学療法や放射線治療が効果を示さなかった患者さま
がんが進行し、従来の治療が効果を示さなかった場合、抗体療法が新たな治療選択肢となる可能性があります。
- 免疫チェックポイント阻害薬が有効な遺伝子変異を持つ患者さま
例として、MSI-H(マイクロサテライト不安定性高)やTMB高値(高い腫瘍変異負荷)などの遺伝子変異を有するがんは、
免疫チェックポイント阻害薬による治療が有効とされています。
- 副作用を抑えながら効果的な治療を希望する患者さま
抗体療法は従来の化学療法と比べて正常細胞への影響が少ないため、副作用を抑えた治療が可能です。そのため、化学療法の副作用に耐えられない患者さまにとって、有力な選択肢となります。
抗体療法と免疫療法の違い
抗体療法は、がん細胞を特定の標的に絞って攻撃するのに対し、免疫療法は免疫機能全体を強化し、がん細胞を排除することを目的としています。
| 項目 | 抗体療法 | 免疫療法 |
| 作用の仕組み | がん細胞の特定の分子(HER2、EGFR など)を標的に攻撃 | 免疫細胞(T細胞・NK細胞など)を活性化し、がん細胞を攻撃 |
| 目的 | がん細胞の増殖を直接抑制、または免疫細胞を誘導して攻撃 | 免疫システム全体を強化し、がん細胞を排除 |
| 治療対象 | 特定の分子(抗原)を持つがん(HER2陽性乳がんなど) | 免疫応答が有効ながん(肺がん・腎細胞がんなど) |
| 代表的な治療法 | 分子標的治療薬、抗体薬物複合体(ADC) | 免疫チェックポイント阻害薬、CAR-T細胞療法、ワクチン療法 |
| 代表的な薬剤 |
|
|
| 長所 | 正確にがん細胞を狙い撃ちできるため、副作用が比較的少ない | 免疫システムを活用し、長期的ながん抑制が可能 |
| 短所・副作用 | がん細胞が耐性を持つ可能性がある | 自己免疫反応による副作用(間質性肺炎、甲状腺障害 など)が発生することがある |
抗体療法と6種複合免疫療法
抗体療法は、がん細胞の特定の分子(抗原)を標的とする治療法ですが、単独では効果が限定的な場合があります。
そのため、近年では「6種複合免疫療法」と組み合わせることで、治療効果を向上させる試みが進められています。
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を体外に取り出し、6種類の免疫細胞を同時に活性化・増殖させてから体内に戻す治療法です。
これにより、免疫システム全体を強化し、がん細胞への攻撃力を高めることが期待されます。
| 免疫細胞の種類 | 役割・機能 |
| キラーT細胞 | がん細胞を直接攻撃・破壊する |
| NK細胞(ナチュラルキラー細胞) | がん細胞を見つけ次第、即座に攻撃する |
| NKT細胞 | キラーT細胞とNK細胞の両方の性質を持ち、がん細胞を攻撃しつつ、他の免疫細胞を活性化 |
| γδT細胞 | 強力な抗腫瘍作用を持ち、がん細胞の排除に寄与 |
| 樹状細胞 | がん細胞の情報を他の免疫細胞に伝達し、免疫反応を促進 |
| ヘルパーT細胞 | 免疫の司令塔として、他の免疫細胞に攻撃の指令を出す |
抗体療法との組み合わせのメリット
- がん細胞の標的を狙う抗体療法と、免疫全体を活性化する免疫療法の相乗効果
- 免疫細胞の攻撃力を高め、がん細胞の抵抗性を克服する可能性
- 再発・転移がんにも対応しやすい治療戦略の構築
抗体療法と6種複合免疫療法を組み合わせることで、がん細胞を直接攻撃しながら、免疫システムを総合的に活性化することが可能となります。
今後の研究により、さらに有効な治療法の開発が期待されています。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00