がん患者様のためのお役立ちブログ


抗がん剤の副作用軽減の方法とは?
抗がん剤治療では、吐き気や脱毛、倦怠感、口内炎、下痢・便秘、免疫力低下、手足のしびれ、食欲不振・味覚変化、皮膚・爪の変化など、様々な副作用が現れることがあります。
これらの副作用は、適切な対策を行うことで軽減できるものも多くあります。
今回の記事では、具体的な軽減策について詳しく解説します。
【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
INDEX
抗がん剤副作用の種類と軽減策
抗がん剤治療は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼすため、さまざまな副作用が現れます。
症状の出方には個人差がありますが、適切な対策を取ることで軽減できるものも多くあります。
吐き気・嘔吐
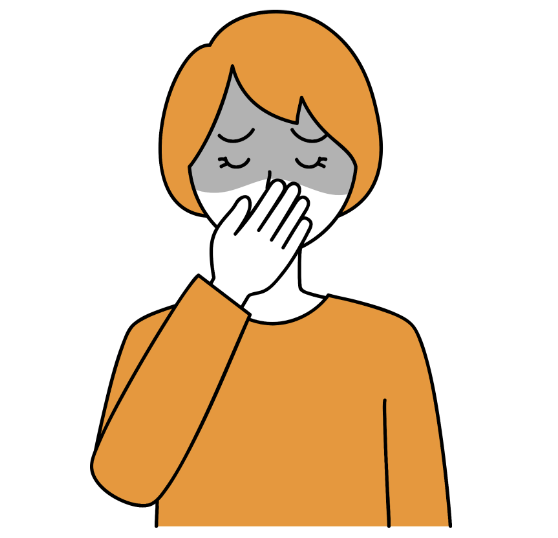
抗がん剤による吐き気や嘔吐は、脳の嘔吐中枢や消化管の神経が刺激されることが主な原因です。
特に、消化器系(胃がん、大腸がん、膵がん)や肺がんの治療で使用される抗がん剤で起こりやすく、治療開始直後から数日間続くことがあります。
また、精神的な不安やストレスが症状を悪化させることもあります。
ここでは、吐き気や嘔吐の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 薬物療法 | 制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬、ステロイド、NK1受容体拮抗薬)の使用 |
| 食事の工夫 | 消化の良い食品を選び、少量ずつこまめに食べる |
| 水分補給 | 少量ずつ頻繁に飲み、脱水を防ぐ |
| 環境調整 | 強いにおいを避け、換気の良い空間でリラックスする |
| リラックス法 | 深呼吸やアロマテラピー、ツボ押しを取り入れる |
吐き気や嘔吐は、適切な制吐剤の使用や生活習慣の工夫により軽減できる場合が多いため、医師と相談しながら最適な方法を見つけることが重要です。
倦怠感・疲労
抗がん剤治療による倦怠感や疲労は、骨髄抑制による貧血、免疫機能の低下、筋力の減少、食欲不振による栄養不足などが主な原因です。
また、治療に伴うストレスや不安も影響し、長期間にわたって続くことがあります。
特に血液がん(白血病・悪性リンパ腫)、肺がん、乳がんの治療では、強い倦怠感を訴えるケースが多いです。
以下、倦怠感・疲労感の軽減方法を紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 適度な運動 | 軽いストレッチや散歩で筋力低下を防ぐ |
| 栄養バランスの取れた食事 | 鉄分やタンパク質を意識的に摂取し、エネルギーを補う |
| 十分な休息 | 規則正しい生活を心がけ、必要に応じて昼寝を取り入れる |
| ストレス管理 | 瞑想や深呼吸、趣味の時間を確保し、リラックスする |
| 医師との相談 | 貧血や甲状腺機能低下の可能性を確認し、必要に応じて治療を受ける |
倦怠感は、生活習慣の工夫や医療的サポートによって軽減できることが多いです。
脱毛
抗がん剤による脱毛は、がん細胞だけでなく、成長が早い正常な細胞にも影響を及ぼすために起こります。
特に毛根の細胞がダメージを受けることで、髪の毛が抜けやすくなります。
乳がん、血液がん(白血病・悪性リンパ腫)、肺がん、大腸がんなどの治療で使用される特定の抗がん剤(アントラサイクリン系・タキサン系など)は、脱毛が起こりやすいとされています。
以下、脱毛の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 頭皮冷却療法 | 治療中に頭皮を冷やし、血流を抑えて脱毛を軽減する |
| 優しく髪を扱う | 強いブラッシングや高温のドライヤーを避ける |
| 保湿ケア | 頭皮の乾燥を防ぐため、低刺激のシャンプーを使用する |
脱毛は治療後に回復することがほとんどですが、事前の準備や適切なケアを行うことで、ストレスを軽減し、より快適に過ごすことができます。
口内炎・口の乾燥
抗がん剤治療によって口の粘膜の細胞がダメージを受けると、口内炎や口の乾燥が起こりやすくなります。
また、唾液の分泌が減少することで細菌が増えやすくなり、炎症や痛みを伴うこともあります。
特に頭頸部がん、血液がん、乳がんなどの治療で発生しやすい副作用の一つです。
以下、口内炎・口の感想の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 口腔ケアを徹底 | 柔らかい歯ブラシを使用し、こまめにうがいをする |
| 刺激の少ない食事を選ぶ | 酸味や辛味の強い食品を避け、ぬるま湯やスープなどを摂取する |
| 水分補給を心がける | こまめに水やお茶を飲み、口内の乾燥を防ぐ |
| 保湿剤の活用 | 唾液の代わりになるジェルやスプレーを使用する |
| 医師の相談 | 痛みが強い場合は、口内炎用の薬や保湿剤を処方してもらう |
口内炎や口の乾燥は、適切なケアを行うことで症状を和らげることができます。食事や口腔ケアを工夫しながら、口の健康を保つことが大切です。
下痢・便秘

抗がん剤は消化管の粘膜細胞にも影響を与えるため、腸の機能が乱れやすくなり、下痢や便秘を引き起こすことがあります。
特に大腸がん、膵がん、血液がんの治療では、腸の動きが過剰になったり、逆に低下したりすることがあり、症状が出やすくなります。
また、抗がん剤の種類や併用する薬剤(鎮痛薬など)も便通の変化に関与することがあります。
以下、下痢・便秘の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 食事の調整 | 下痢の場合は消化の良い食品(おかゆ、スープなど)、便秘の場合は食物繊維を含む食品(野菜、ヨーグルトなど)を摂取 |
| 水分補給 | 下痢による脱水を防ぐため、こまめに水分を摂る |
| 適度な運動 | 腸の働きを整えるために、軽いウォーキングを取り入れる |
| 薬の使用 | 下痢止めや緩下剤を、医師の指示のもと適切に使用する |
| ストレス管理 | 自律神経の乱れを防ぐため、リラックスする時間を作る |
便通の異常は日常生活に大きく影響を及ぼすため、食事や運動の工夫、必要に応じた薬の使用で早めに対策を取ることが大切です。
免疫力の低下
抗がん剤はがん細胞だけでなく、白血球などの免疫細胞も攻撃するため、免疫力が低下しやすくなります。
特に、血液がん(白血病・悪性リンパ腫)、乳がん、肺がんの治療では、白血球の減少が顕著になり、感染症のリスクが高まります。
また、治療に伴う栄養不足や疲労も免疫機能を低下させる要因となります。
以下、免疫力低下の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 手洗い・うがいの徹底 | こまめな手洗い・うがいで細菌やウイルスの感染を防ぐ |
| バランスの取れた食事 | たんぱく質やビタミンを含む食品を積極的に摂取する |
| 人混みを避ける | 免疫が低下している間は、感染リスクの高い場所を控える |
| 適度な休息と運動 | 睡眠を十分に取り、軽い運動で体力を維持する |
| 白血球増加剤の活用 | 必要に応じて、医師の指示のもと白血球を増やす薬を使用する |
免疫力の低下は感染症のリスクを高めるため、日常の生活習慣を見直すことが重要です。
手足のしびれ(末梢神経障害)
抗がん剤の中には神経細胞に影響を与えるものがあり、手足のしびれや感覚異常を引き起こすことがあります。
特にタキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル)やプラチナ系(シスプラチン、オキサリプラチン)の抗がん剤で起こりやすく、乳がん、大腸がん、肺がん、卵巣がんなどの治療を受ける患者さまに多く見られます。
症状が進行すると、物をつかみにくくなったり、歩行が困難になることもあります。
以下、しびれの軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 手足を冷やしすぎない | 末梢の血流を良くするために、防寒対策を行う |
| 軽いマッサージやストレッチ | 血流を促し、神経の回復を助ける |
| ビタミンB群の摂取 | 神経の修復をサポートする食品(豚肉、大豆、ナッツ類)を取り入れる |
| 医師と相談しながら投与量を調整 | 症状が重い場合は、抗がん剤の量を調整する可能性がある |
| リハビリの実施 | 症状が進行した場合、作業療法や理学療法を取り入れる |
手足のしびれは治療後も続くことがありますが、早めの対策や生活習慣の改善により、症状を軽減できる可能性があります。
食欲不振・味覚の変化
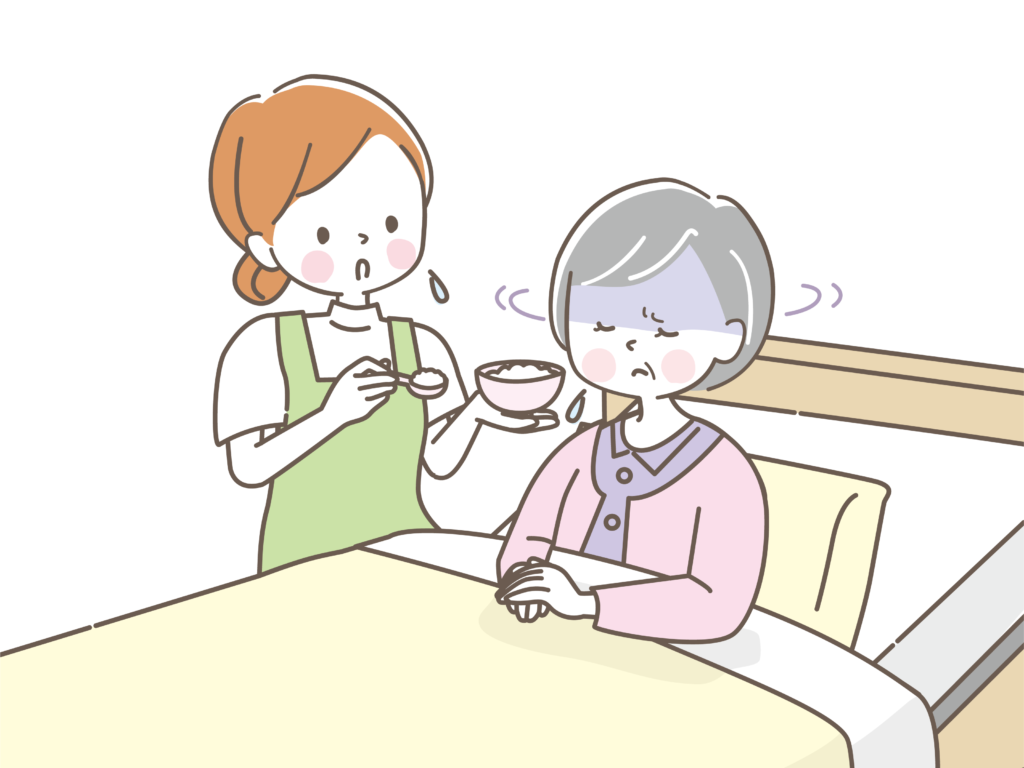
抗がん剤治療中は消化器の機能低下やホルモンバランスの変化により、食欲が落ちることがあります。
また、抗がん剤が味覚を感じる細胞に影響を与えることで、食べ物の味が変わることもあります。
特に胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんの治療では、食欲不振や味覚異常が出やすいとされています。味が薄く感じる、苦味や金属のような味がするなどの症状が現れることもあります。
以下、食欲不振・味覚の変化の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 食事の工夫 | さっぱりした味や香りの良い食材(レモン、ショウガ)を活用 |
| 少量ずつこまめに食べる | 無理に食べず、消化の良いものを少しずつ摂取 |
| 冷たい食品を取り入れる | 温かい食べ物よりも、冷やした方が食べやすいことがある |
| 食器を工夫する | 金属の味を避けるため、プラスチック製のスプーンやフォークを使用 |
| 栄養補助食品を活用 | 食事量が少ない場合は、栄養補助飲料やゼリーを取り入れる |
食欲不振や味覚の変化は、治療が終わると回復することが多いですが、その間の栄養不足を防ぐことが重要です。
無理に食べるのではなく、自分に合った食べ方を見つけることが大切です。
皮膚・爪の変化(乾燥・ひび割れ・色素沈着)
抗がん剤は皮膚や爪の細胞の新陳代謝にも影響を与えるため、乾燥やひび割れ、色素沈着、爪の変色・割れなどの症状が現れることがあります。
特に分子標的治療薬(EGFR阻害剤)やプラチナ系抗がん剤(シスプラチン、オキサリプラチン)では、皮膚や爪のトラブルが起こりやすく、乳がん、大腸がん、肺がん、胃がんの治療でみられることが多いです。
以下、皮膚・爪の変化の軽減方法をいくつか紹介します。
| 方法 | 具体的な対策 |
| 保湿を徹底する | 低刺激の保湿クリームを使用し、乾燥やひび割れを防ぐ |
| 日焼け対策を行う | 色素沈着を防ぐために、紫外線対策(帽子・日焼け止め)を実施 |
| 爪のケアを行う | 爪を短く切り、衝撃を避けるために保護剤を使用する |
| 刺激の強い洗剤を避ける | 手袋を使い、皮膚や爪への負担を減らす |
| 皮膚科で相談する | 重症化する前に、保湿剤や外用薬を処方してもらう |
日々の保湿や予防策を徹底し、症状が進行しないように気を付けましょう。
抗がん剤副作用の期間
抗がん剤の副作用は、薬剤の種類や個人の体質によって異なりますが、治療開始直後から数週間~数か月続くことが一般的です。
急性の副作用(吐き気、下痢、倦怠感など)は治療直後に現れ、比較的短期間で回復します。
一方、脱毛や末梢神経障害、味覚の変化などは長期にわたる場合もあります。
治療終了後も影響が残ることがあり、回復には個人差があります。
抗がん剤以外の治療法

抗がん剤治療は、がん細胞を攻撃する一方で正常な細胞にも影響を及ぼし、副作用が発生します。
そのため、副作用を抑えながらがんの進行を抑制するために、抗がん剤以外の治療法が選択されることもあります。
| 治療法 | 特徴・副作用の軽減策 |
| 手術 | がんを物理的に切除する方法。早期がんには有効だが、術後の痛みや回復期間が必要。リハビリを活用し回復を促進。 |
| 放射線治療 | がん細胞を局所的に破壊。皮膚炎や倦怠感が副作用として現れることがあり、保湿ケアや栄養管理が重要。 |
| 分子標的治療 | がん細胞特有の分子を狙う治療。副作用は抗がん剤より軽いが、皮膚障害などが発生することがある。スキンケアや保湿で対応。 |
| 免疫療法 | 体の免疫を活性化し、がんを攻撃。自己免疫反応による副作用が出ることがあり、定期的な検査と経過観察が必要。 |
抗がん剤以外の治療法は、副作用の種類や程度が異なるため、患者さまの状態に応じて最適な治療を選択することが重要です。
副作用の管理を適切に行いながら、治療を継続していくことが求められます。
近年注目されているのは、研究が進み、より高い治療効果が目指されている免疫療法の一つ、「6種複合免疫療法」です。
6種複合免疫療法は、がん免疫療法の1つで、私たちの体の中にある免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻し、がんと闘う力を増強させる療法です。
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、副作用がほとんどなく、体への負担が少ないという特徴があります。
以下、6種複合免疫療法について詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








