がん患者様のためのお役立ちブログ


抗がん剤による口内炎とは
抗がん剤治療では、吐き気や脱毛といった副作用に加えて、口内炎もよく見られる症状の一つです。
食事がしにくくなったり、話すことすらつらく感じたりと、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
しかし、口内炎は適切なケアを行うことで、痛みや不快感を和らげることが可能です。
この記事では、抗がん剤によって起こる口内炎の原因や特徴、そして日常生活で取り入れやすい対処法について、わかりやすく解説します。
また、抗がん剤に頼らずにがんと向き合う方法として注目されている「免疫療法」についても、代表的な治療法やその特徴をあわせてご紹介します。
【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
INDEX
抗がん剤の副作用

抗がん剤は、がん細胞の増殖を抑える強力な薬ですが、同時に正常な細胞にも影響を及ぼすため、さまざまな副作用が現れることがあります。
特に影響を受けやすいのは、細胞分裂が活発な組織で、口腔粘膜や消化管、毛根、骨髄などが代表的です。
抗がん剤による主な副作用は、以下のとおりです。
| 副作用の種類 | 主な症状や影響 |
| 消化器症状 | 吐き気、嘔吐、下痢、食欲不振など。治療初期から現れることが多い。 |
| 骨髄抑制 | 白血球・赤血球・血小板の減少により、感染症や貧血、出血傾向のリスクが高まる。 |
| 脱毛 | 毛根の細胞がダメージを受け、治療中に一時的な脱毛が起こる。 |
| 口内炎・口腔トラブル | 粘膜の炎症や痛みにより、食事や会話が困難になることがある。 |
これらの副作用はすべての患者さまに起こるわけではなく、症状の程度やタイミングには個人差があります。
特に口内炎は早期対処をすることで防ぐことができるため、早めの対策とケアが重要です。
抗がん剤治療で口内炎になるのはなぜ?

抗がん剤治療中に口内炎ができるのは、薬の作用ががん細胞だけでなく、口の中の正常な粘膜細胞にも及ぶためです。
口腔内の粘膜は細胞の新陳代謝が非常に活発な部位のひとつです。そのため、抗がん剤の影響を受けやすく、細胞が傷つくことで炎症が起こりやすくなります。
また、抗がん剤は免疫力を低下させる作用もあるため、普段は問題にならないような細菌や真菌が繁殖しやすくなり、炎症を引き起こすこともあります。
口内炎の主な原因は以下のとおりです。
| 原因 | 説明 |
| 粘膜細胞の傷害 | 抗がん剤が粘膜の細胞分裂を阻害し、薄くもろくなった粘膜が炎症を起こす。 |
| 免疫低下による感染リスク増加 | 菌やカビが繁殖しやすくなり、二次的な感染によって炎症が悪化することがある。 |
| 唾液分泌の減少 | 抗がん剤の影響で唾液の分泌が減ると、口腔内が乾燥して粘膜が傷つきやすくなる。 |
このように、さまざまな要因で口内炎が起きるため、治療中は早めの予防と対処が大切です。
抗がん剤による口内炎はいつ頃できる?
抗がん剤治療にともなう口内炎は、治療開始から5~10日後に現れることが多いとされています。
これは、抗がん剤が粘膜の再生能力に影響を与え、時間差で症状として現れるためです。
ただし、発症時期は薬剤の種類や体質によって個人差があります。また、再発しやすい副作用のひとつでもあるため、定期的な口腔チェックとケアが大切です。
口内炎への心構えと対策
抗がん剤治療中に起こる口内炎は、軽視できない副作用のひとつです。痛みやしみる感覚によって、食事や会話がしにくくなり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。
症状が強くなると、痛みによるストレスや体力低下につながり、治療の継続にも影響を及ぼす可能性もあるため、予防や早期対処に努めることが重要です。
まず大切なのは、「口内炎は誰にでも起こり得るもの」と受け止めることです。
多少の違和感でも「大したことはない」と我慢せず、早い段階で医療者に相談することで、悪化を防ぎやすくなります。
口内炎の予防と対策のポイントは以下のとおりです。
| 対策 | 内容 |
| 口腔ケアを徹底する | やわらかい歯ブラシを使い、1日数回の丁寧な歯磨きと定期的なうがいを心がける。口腔内を清潔に保つことが基本。 |
| 刺激の少ない食事を選ぶ | 辛いもの、酸味の強いもの、熱すぎる・冷たすぎるものは避け、やわらかく飲み込みやすい食事を心がける。 |
| 保湿を意識する | 唾液の分泌を促したり、保湿ジェルを使用したりして、口腔内の乾燥を防ぐ。 |
| 早めに医師に相談する | 鎮痛薬や粘膜保護剤、抗菌薬などを使用して、症状をやわらげたり、感染を予防したりする。 |
また、治療開始前に歯科での口腔チェックを受けておくと、リスクのある部位を事前に把握でき、口腔内トラブルを未然に防ぐためのケアへとつながります。
口内炎が悪化すると、治療の継続に影響を及ぼす可能性もあるため、「早めの対応」と「日常的なケア」を意識して過ごすことが大切です。
口内炎に悩まない|抗がん剤以外の治療法の選択肢
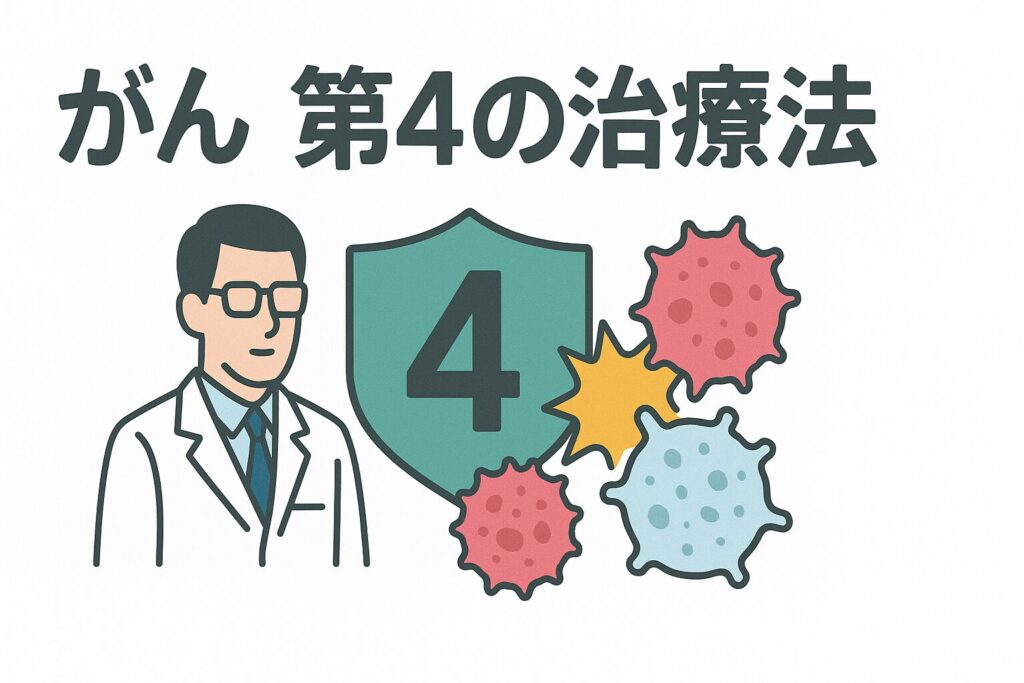
抗がん剤による口内炎に悩まされることなく治療を継続したいという方には、免疫の力を利用した治療法という選択肢もあります。
ここでは、抗がん剤に頼らずにがんと向き合うための、代表的な免疫療法についてご紹介します。
樹状細胞ワクチン療法
樹状細胞ワクチン療法は、がんに対する免疫反応を高めることを目的とした治療法です。樹状細胞は免疫の「指令役」とも呼ばれる細胞で、がん細胞の情報をT細胞に伝える重要な働きを担います。
この治療では、患者さま自身の血液から樹状細胞を取り出し、そこにがん抗原を取り込ませてから体内に戻します。これにより、免疫システムががん細胞を認識し、攻撃する力を高めることができます。
抗がん剤のような全身への強い影響が少ないため、副作用が比較的少なく、体への負担が軽い点も特長です。現在は、さまざまな固形がんに対して応用が進められています。
活性化Tリンパ球療法
活性化Tリンパ球療法は、患者さま自身の血液から採取したTリンパ球を体外で活性化・増殖させ、再び体内に戻すことでがんと闘う力を高める免疫療法です。Tリンパ球は、本来がん細胞を直接攻撃する能力を持つ免疫細胞であり、この治療ではその働きをさらに強化することが目的です。
患者さま自身の細胞を用いるため、拒絶反応や重篤な副作用が起こりにくい治療法とされています。また、抗がん剤と比べて体への負担が少ないため、治療中も比較的体調を維持しやすい点が特長です。
Tリンパ球の力を利用して、がん細胞を見つけて排除する能力を高めるこの治療法は、再発予防や進行の抑制を目的とするケースでとくに注目されています。「自分自身の免疫力を活かす」ことに重点を置いた選択肢として、多くのがん患者さまに支持されている治療法のひとつです。
アルファ・ベータT細胞療法
アルファ・ベータT細胞療法は、T細胞の中でも特に免疫応答の中心を担う「αβT細胞」を活用する治療法です。
この細胞は、がん細胞の特徴を的確に識別し、特定の抗原に対して強力な攻撃を仕掛ける能力があります。この治療では、患者さま自身の体からαβT細胞を採取し、体外で活性化・増殖させたのちに再び体内へ戻すことで、がんに対する免疫反応を強化します。
αβT細胞は、標的への高い特異性を持ち、正常な細胞への影響を最小限に抑えつつ、がん細胞を的確に攻撃する点が大きな特徴です。また、一度活性化されたT細胞は、体内で長期間にわたって働き続けられる可能性があり、持続的な治療効果も期待されています。
自己由来の細胞を用いるため、拒絶反応や重篤な副作用のリスクも比較的低く、安全性の面でも安心できる治療法です。また、他の免疫療法と組み合わせることで、相乗的な効果が得られる可能性もあり、がん治療の新たな選択肢として注目されています。
ガンマ・デルタT細胞療法
ガンマ・デルタT細胞療法は、「γδT細胞(ガンマ・デルタT細胞)」を活用した免疫療法です。この細胞は、がん細胞の異常を抗原提示に頼らずに直接認識し、速やかに攻撃できる特徴を持っています。γδT細胞は自然免疫と獲得免疫の両方の性質を持っており、即時的かつ柔軟にがんへ反応できる点が特長です。
抗原依存性が低いため、がん細胞を特定の目印に頼らずに認識でき、さまざまながん種に対して幅広く対応できます。また、活性化までのスピードが早く、治療開始から比較的短期間で効果が期待される即応性にも優れています。さらに、自己の細胞を使用することで副作用が少なく、長期的な治療にもつながる可能性があります。
現在も研究が進められており、将来的に多くのがん患者さまに貢献する可能性を持つ治療法として注目されています。
NK細胞療法
NK細胞療法は、生まれつき体内に存在する「ナチュラルキラー(NK)細胞」の力を利用した免疫療法です。NK細胞は、抗原提示がなくても異常な細胞を即座に見つけて攻撃できる自然免疫の一種で、がん細胞やウイルス感染細胞に対して広く反応します。
この治療では、患者さま自身のNK細胞を活性化・増殖させて体内に戻すことで、がん細胞の排除を促進します。治療効果が現れるまでのスピードも早く、ほかの免疫細胞の働きをサポートする役割も期待されています。自己由来の細胞を使用するため拒絶反応が起こりにくく、副作用が比較的少ない点も大きな利点です。
体本来の防御力を引き出す補完的な治療法として、がん治療に導入されるケースが増えています。
6種複合免疫療法
6種複合免疫療法は、がんに対する免疫応答を最大限に引き出すことを目指す免疫療法です。その名の通り、役割の異なる6種類の免疫細胞を活性化・補充することで、がんに対して多方向からアプローチするのが特長です。
この療法では、「攻撃」「指令」「監視」といった異なる役割を持つ免疫細胞が連携し、がんに対する総合的な防御体制を構築します。例えば、T細胞ががん細胞を攻撃する一方で、樹状細胞が情報を伝達し、NK細胞が即時的な対応を担うなど、複数の免疫メカニズムが同時に働きます。
単一の免疫療法では得られにくかった持続的な治療効果や、さまざまながん種に対応できる高い汎用性が期待されており、体への負担を抑えつつ免疫力を根本から高める治療法として注目されています。
副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-350-552
受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00
土曜/09:00 - 13:00








